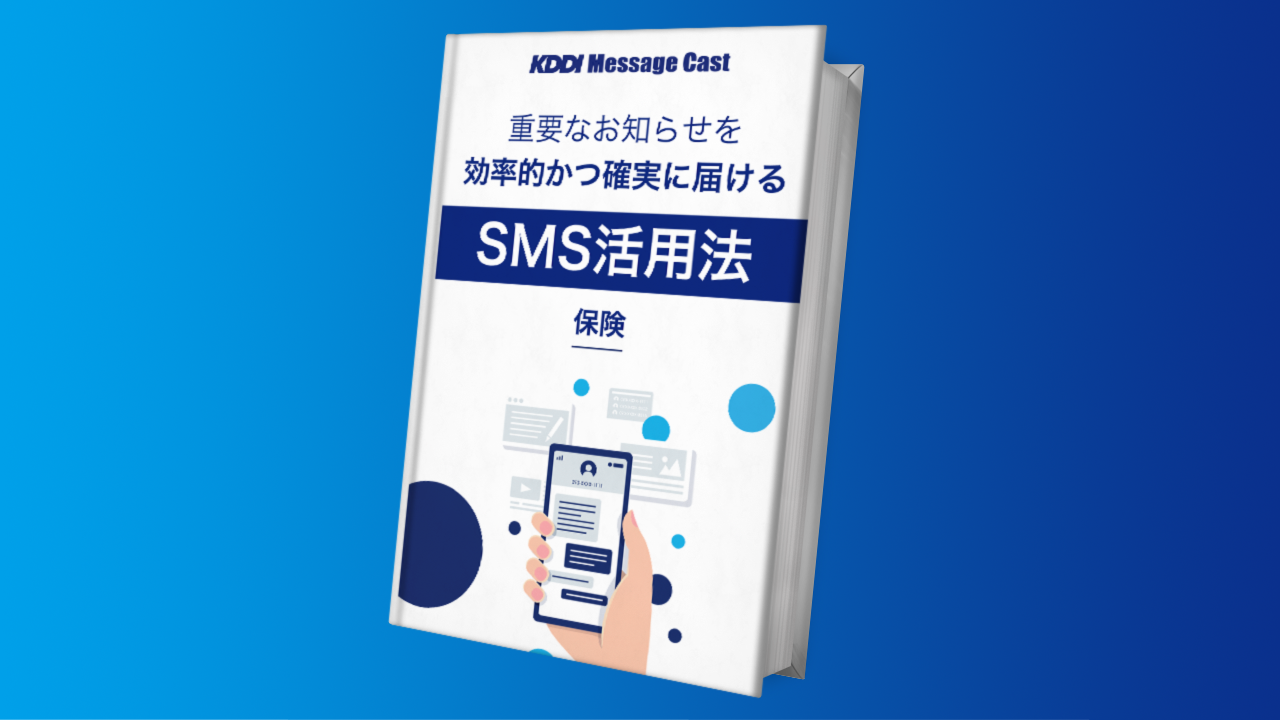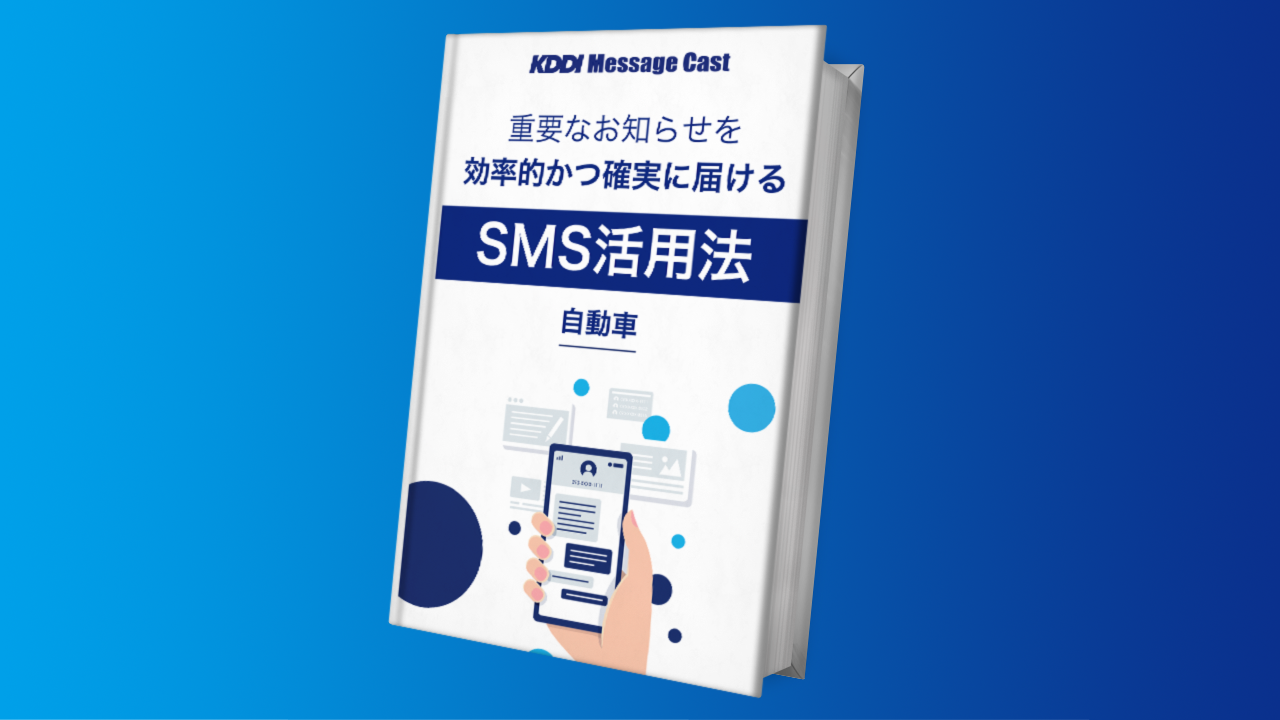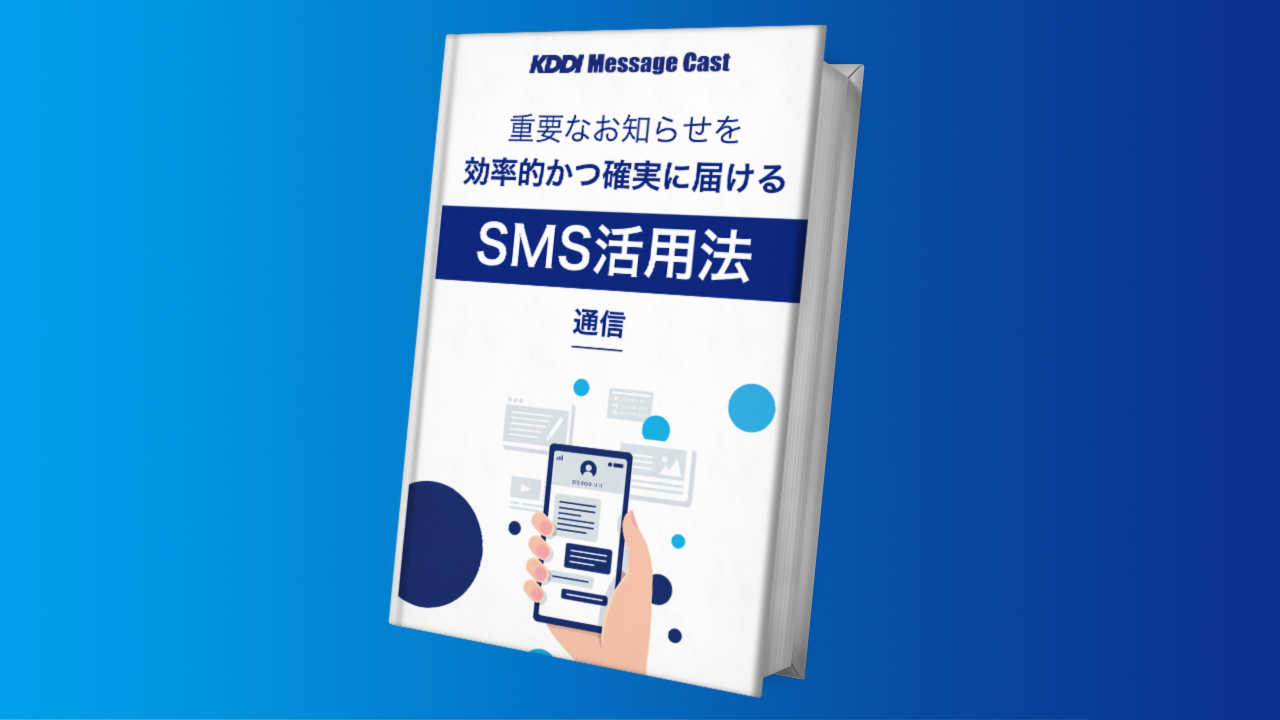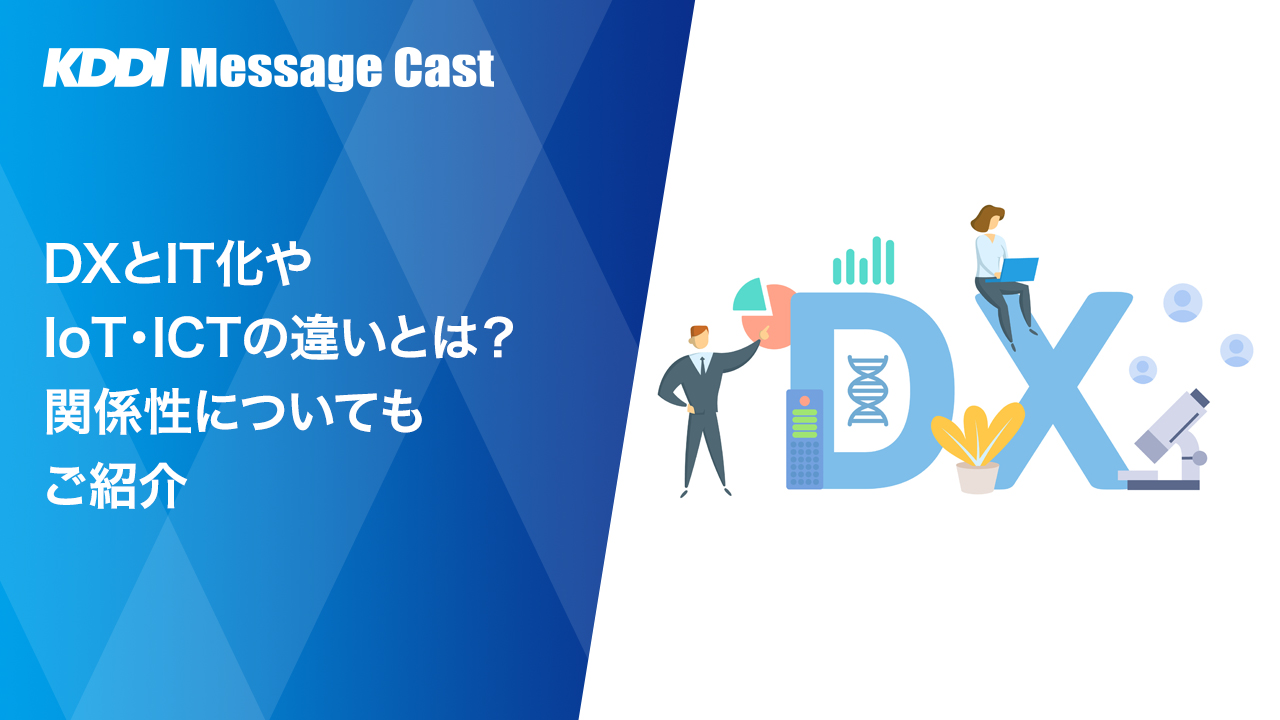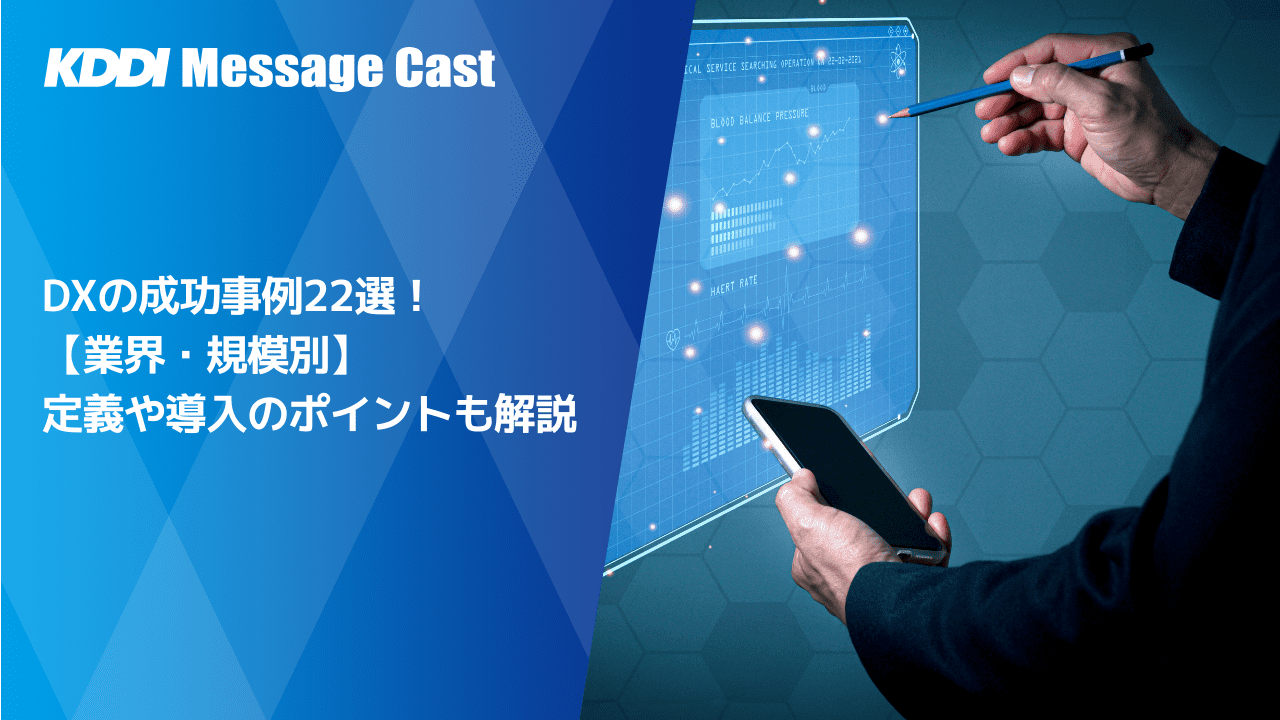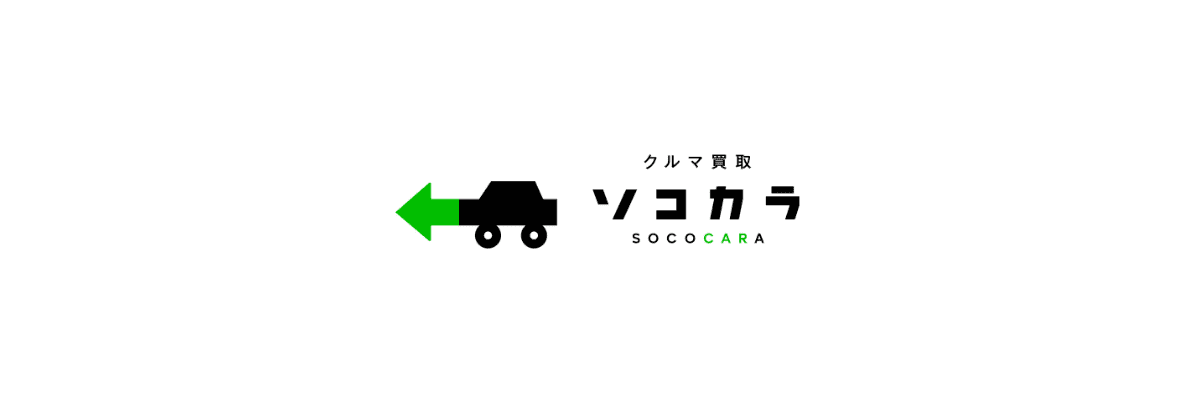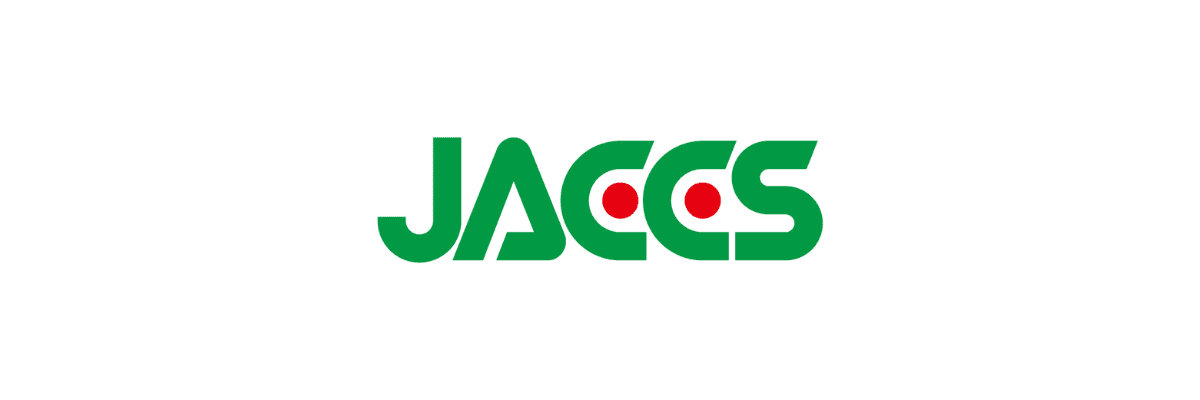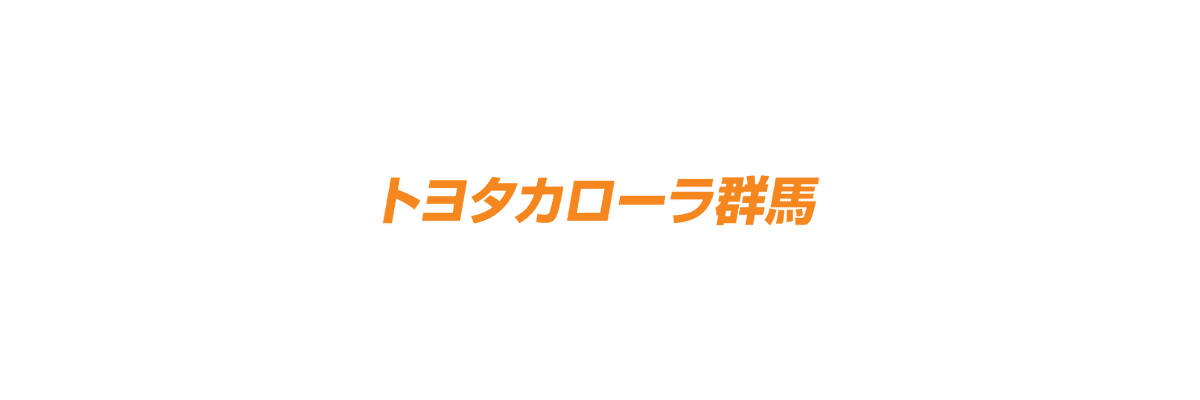建設DXとは?導入メリットや課題は?DX化の進め方や事例を紹介


ビジネス環境が大きく変化している近年、デジタルの活用による業務効率化、新しい働き方を含めた事業運営体制の構築などを目標として、DXの推進が加速しています。特に高齢化や人手不足、熟練技術の継承などの業界特有の課題を抱えている建設業界では、課題解決策として建設DXに期待が集まっています。
本記事では、建設DXの概要、建設業界でDXが注目される背景、建設業の特徴と課題、DX技術などについて解説します。建設DX推進に向けた国の取組事例もご紹介しています。
目次
そもそも建設DXとは


建設DXとは、デジタル技術を活用し、建設業でこれまで行われていた業務プロセスをはじめとして、ビジネスそのものを根本から変革することです。仕事のやり方そのものを変えていくことで、建設業界が抱えている人手不足や労働生産性の低さといったさまざまな問題を解決し、新たな強みにしていくことが目標です。こうした取り組みは大手の建設企業から始まっていますが、ベンチャーやスタートアップなど小規模の企業でもDXで成果をあげている事例もあります。全国各地で開かれている建設DXに特化した展示会なども盛況です。
DXとは何か
DXとは”Digital Transformation”の略で、「デジタル・トランスフォーメーション」と読みます。企業がデジタル技術を活用して、業務フローの改善から企業風土の変革まで実現させることです。スウェーデンの大学教授が提唱した考え方で、「IT(情報技術)の浸透が、あらゆる面で人々の生活を良い方向に変化させる」という内容でした。ただし、DXは単に変革を意味するのではありません。既存の価値観や枠組みも含め、根底から変えていく革新的なイノベーションを指します。
関連リンク:DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?DX推進のメリットと課題も解説
建設業のDX化が進まない理由
建設業ではIT導入をする傾向が生まれていますが、DXを実現するほどのイノベーションはあまり進んでいません。資金的に厳しく、DXに向けて大きな投資をすることが難しい企業も多いのは確かです。しかし、抜本的な原因はDXを推進しにくい現場環境があることです。
建設業界ではアナログ作業が中心になっている影響で、DX化を進めにくい状況があります。建設現場における作業は人の手による作業が基本です。ロボットやドローンなどの導入をしたり、施工管理や品質管理のIT化を推進したりすることに対して抵抗感を持つ人が多く、改革を進めにくい環境になっています。
また、アナログ作業に慣れている影響もあって、全体的にITリテラシーが低いことも課題です。DXを推進する上では、IT活用や情報漏えいなどのリスクがあり、ITリテラシー教育の方法を検討しなければなりません。
建設業界においてDXが注目される背景
少子高齢化が進んでいる日本では、人口の減少にともない労働人口も減少していることが大きな社会課題となっています。厚生労働省による日本の人口の調査・推計によると、2010年を境に、人口減少の方向に進んでいます。2040年には2020年に比べて約90%の人口になり、2070年には約69%にまで人口減少が起こると推計されています。
この傾向は建設業界でも顕著で、人手不足の問題がより深刻になってきています。少子高齢化が加速する中では、働き手の大幅な増加は見込めないため、人員を割くことなく、同じ作業を続けられるかが鍵です。さらに、インフラの老朽化が進む一方、公共事業費の縮小により、予算も人員も十分に確保できない状況にあり、重大な事故も発生し始めています。そのため、インフラの点検やメンテナンスをDXで省力化・効率化していくことに注目が集まっているのです。このような背景から、DXは建設業でも推進が求められています。
建設業の特徴と課題


建設業は、基本的に屋外で作業する仕事が中心です。発注先から発注を受けて構造物をつくる受注産業です。仕事の現場が事務所から離れているため、機械化により効率化するのが難しいことが特徴の一つといえます。また、一つのプロジェクトに多数の関係者が関わりますが、現場は下請けや孫請け企業の作業員が対応します。建設DXは、元請けだけが進めても下請けが動かなければ、全プロジェクトの効果は限定的なものになるでしょう。
建設現場の仕事では、設計図面を読んだり、必要な部材を組み上げたり、その場で部材の加工を行うこともあり、幅広い技能が必要です。また、鉄筋工事にも木造建築にも、独自のノウハウがあり、さらに企業によっても異なります。
以上が建設業の主な特徴ですが、建設業が抱えている課題についても見ていきましょう。
労働生産性が極めて低い
一般社団法人日本建設業連合会による建設業デジタルハンドブックには労働生産性についての統計データが記載されています。付加価値労働生産性について建設業では3,000円/人・時間程度です。全業種における平均値は4,500円/人・時間なので大きな差があります。
アナログな仕事が根強く残る建設業では、いまだに図面や報告書などに紙が使われているケースが多く見られます。紙の報告書の場合、変更が入った場合に関係する箇所の紙面をすべて修正する必要があり、時間も手間もかかってしまい、労働生産性が低いと言わざるを得ません。
建設業の場合、現場ごとで業務や作業が違うことや、手作業が多いことも要因です。また、プロセスが細かく分割されていて、それぞれのプロセスにたくさんの人が関わっているため、情報伝達などに手間がかかることなども問題として挙げられています。
参照:5. 生産性と技術開発 | 建設業の現状 | 日本建設業連合会
人材不足
人材不足は多くの業界で課題となっていますが、全産業の中でもとくに建設業では深刻な状況です。建設業者就業者数は令和3年度の時点で485万人程度で、近年で最も多かった平成9年度よりも29%ほど減少しています。
人材不足が技能承継の遅れの要因にもなっているため、後継者不足から事業継続が難しくなっている企業も少なくありません。建設・建築現場へのマイナスイメージから、若年世代が建設業を進路志望先に挙げていない傾向も人手不足の要因と考えられます。今後も建設業が地域社会を支えていくためには、若年世代が興味を持てるように、建設業に対する旧来からのイメージを払拭する必要があるといえるでしょう。
また、コロナ禍をきっかけに、多くの企業でDX化のニーズが高まっており、DX人材の確保が急務とされています。2020年のDX市場の求人倍率は、前年比をはるかに上回っています。
高齢化が顕著
建設業界の人材問題は、人手不足だけではなく、高齢化も挙げられます。建設業界では、若年労働者の不足が顕著です。就業者のうち若年層が占める割合が年ごとに低下傾向にあり、高齢化が進んでいるのが現状です。高齢者は体力や筋力、判断力などが若い世代より低下してくるため、さまざまなリスクを抱える可能性が多くなってきます。また、積み重ねてきた実務経験や勘による業務がルーティン化すると、業務管理ツールなどのITを活用した新しい取り組みに対応できない可能性が高くなります。
技術継承問題
建設業界では技術継承が大きな課題です。少子高齢化の影響を受けて技術や技能を受け継ぐ人材が減少しています。全体的な人材不足の影響もあって、技術継承に時間を割けない状況もあるのが現状です。技術は伝えるのが難しい面もあり、教育に携わってきた経験がないベテランが若手に教えるのに苦労している状況もあります。
社団法人建設産業専門団体連合会では「建設技能労働力の確保に関する調査報告書」で技能労働者の不足について調査結果をまとめています。平成19年の時点で4年以上前から不足を感じている企業が51%を占めている結果になっています。建設技術の継承の課題は今までと同様の労働環境の改善や採用活動の取り組みによって解決することが難しいのが実情です。
参照:建設技能労働力の確保に関する調査報告書|平成19年3月 社団法人 建設産業専門団体連合会
下請け構造の問題
建設業では重層的な下請け構造が構築されています。一次下請け、二次下請け、三次下請けといった形で多数の関係者が建設の作業や管理に携わる仕組みです。ITリテラシーの理解を全体に浸透させて、共通のシステムで建築業務をおこなうことは容易ではありません。
国土交通省でも重層下請構造の改善に向けた取り組みを進めています。元請け企業と下請け企業がそれぞれの機能を明確化することを促すなど、改善の努力は進められています。しかし、多層構造になっている限りは業務管理も品質管理も難しく、データを集約することも困難です。下層に位置する下請け企業の負担も大きくなるため、資金的に経営を続けられなくなる企業もあります。
建設DXの導入メリット
DXを取り入れることで、業務の効率化、省人化、技術継承が進み、建設業界のさまざまな課題解決につながります。各メリットについて解説します。
関連リンク:DX化とIT化やIoT・ICTの違いとは?DX化のメリットや課題について解説
業務の効率化
デジタル化の促進により、これまで人手がかかっていた業務の自動化や、業務共有などが可能になります。例えば、図面の共有はタブレットやPCで確認でき、締結作業は電子契約を導入することで簡略化が可能です。また測量データや図面などをもとに3次元モデルを作成し、意匠や構造・設備設計、コストなどの情報も落とし込んで一元管理することができます。その結果、関係者同士が建設現場に行かなくてもリモートで画面を使いながら仕様の打合せなどができるようになり、迅速な確認プロセスが可能です。作業員の進捗状況についても把握しやすくなり、効率的な工事管理、安全性の向上が期待できます。
関連リンク:DX推進が業務効率化に繋がるのはなぜ?重要性や成功事例をご紹介
省人化
DXによる省人化効果もメリットです。省人化は、業務効率化のため、工程を減らすことで人手不足の問題を解消する考え方です。例えば、現場の管理や指示などはモニターカメラを使えば、遠隔からでも指示や管理ができます。また、作業現場に人がいなくても、ロボットが資材の運搬などを自動で行うことも可能になるなど、作業が劇的に軽減されます。ロボットやカメラを使えば、深夜の監視や清掃なども可能です。このように、施工状況や指定材料の確認など、従来現場で行っていた業務が事務所で行えるため、少ない人員で作業や業務をこなせます。
技術継承
先述したように、建設業界では高齢化と人材不足により技術継承が難しくなっていますが、こうした問題解決につながるのがDX技術です。DXを活用すると、熟練技術者がどういう情報でどのように判断したかというデータが残るため、社内全体で共有できます。対面で指導を受けなくても、そのモデルを参照すればノウハウを学べるのです。多くの技術者が学ぶことができ、データは後から確認することもできます。
また、職人の動きなどをAIが映像解析して、動きを再現することでも技能継承が可能になってきました。このようにDX技術の導入で、熟練者のノウハウを記録し、デジタルデータ化することで、他の作業員や新人が学べる環境を作ることができるでしょう。
過重労働問題の解消
建設現場における過重労働問題は、DXによって解消できる可能性があります。省人化ができるくらいの建設業務の効率化を進めれば、残業や休日労働を減らせるのは明らかです。2024年4月からは働き方改革関連法の改正によって、時間外労働の法的な制限が加えられます。コンプライアンス遵守のためにも、過重労働問題への対策をDXで実現することは大切です。労務管理システムを運用して従業員の労働時間を自動監視する仕組みを整えることもできます。
建設DX推進に向けた国の取組事例


国土交通省が建設DXを提唱していますが、ここでは国が現在取り組んでいる事例をいくつかご紹介します。
i-Construction
i-Constructionは、国土交通省が掲げる取り組みの一つで、ICTを活用することで建設生産システムの生産性向上を目指すものです。
国土交通省は、以下の3つの施策を進めています。
- IICTの全面的な活用(ICT施工)
- コンクリート工規格の標準化など
- 施工時期の平準化など
ICT施工は、あらゆる建設プロセスでICTを活用し、業務の改革を目指すものです。2025年までに生産性を2割伸ばすため、さまざまな取り組みが行われています。またコスト削減や生産性の向上を目指して、部材のサイズなどの規格を標準化し、工場製作化を進めています。さらに公共工事は4〜6月の第1四半期に工事量が少なく、かなり偏りがあるため、 適正な工期確保のため、2か年国債を設定しました。
引用元:i-Construction
インフラDX 総合推進室の発足
2021年4月1日、国土交通省は「インフラDX 総合推進室」を新設しました。本省・研究所・地方整備局が一体となって共同で建設業のDXを推進する体制が整備されたのです。デジタル技術とデータの活用により新しい働き方や生産性・安全性の向上などを目的としており、インフラ分野のDXに国が動き出したことが示されています。インフラ分野でのDX推進に向けて、環境整備、新技術の導入促進、人材育成などの強化に取り組むとされています。
BIM/CIM
BIM/CIMとは、建設業の計画・設計の段階から3Dデータを用いる取り組み全体のことを指す言葉です。3次元モデルを導⼊し情報を充実させ、事業全体の関係者が情報を共有することで、業務効率化・⾼度化を図ることが目標です。国は2023年度までに、原則小規模工事を除く全ての公共工事でBIM/CIMを適用するとしています。具体的には、オンライン電子納品、リモートによる監督などは速やかに整備して開始し、3D技術に対応可能な人材育成、現場に応用するデジタル技術の開発などを段階的に進めていく予定です。またDXを進めることで、建設業に対して従来からある3Kのイメージの払拭も目指しています。
引用元:BIM/CIMとは
建設DXで用いられる技術とは?


建設DXには具体的にどのような技術が用いられているのか見ていきましょう。
ドローン
無線で遠隔操作されるドローンは、無人の飛行物体です。膨大な日数を要する数百万もの地点の測量データでも、ドローンを使えば15分で取得できます。危険が伴うリスクがある高所や斜面での確認作業も、ドローンを使えば現場で目視する必要がなく、従業員の安全を確保できます。高所の点検作業では、足場の組み立てが必要なことも多く、予算と人手不足が課題でした。しかし、ドローンを活用すると、少人数で安全かつ安価に点検作業ができるため、建設業の働き方改革の役目の一部を担っているといえます。
AI(人工知能)
AIは、人間の思考の一部をシステムで再現する技術です。建設業では、熟練職人の動きなどを映像解析することで技術継承に一役買ったり、3Dモデルデータを処理したり、など幅広い活用が注目されています。とくにAIの画像診断の精度は非常に高いことで知られており、インフラの老朽化の検知や事故防止などでも役立てられています。今後、建設業界でDXの導入が進み、蓄積されるデータがさらに増えてくると、AIの重要性はより増していくでしょう。
クラウドサービス
クラウドサービスは、インターネットを介して使用する会計ソフトやビジネスチャットのような、ソフトウェア全般を指します。施工管理アプリなど、建設業に特化したソフトウェアもあります。データを一元管理したり、ノウハウを共有したりするためには、クラウド型の管理システムが最適です。日々の業務の効率化の基盤となるクラウドサービスは、建設業に限らず、あらゆる産業のDXに貢献しているツールです。
3次元モデルデータ
3次元モデルデータとは、先述しました「国の取組事例」の中でご紹介したi-ConstructionやBIM/CIMの中心となる技術です。3Dデータでは、建設中の構造物の状態をさまざまな角度から確認することができ、これまでの2次元の図面では確認できなかった問題点を発見することが可能です。また、設計、測量、施工、維持管理などの各プロセスに3Dデータを活用することで、情報やイメージの共有ができ、確認や修正面での効率化も期待できます。最近では、特定のスマホやタブレットに搭載されている機能による3次元モデルデータの作成方法が注目されています。
ICT
ICT(情報通信技術)はITによるコミュニケーションを実現する技術です。広い意味ではスマートフォンによる通話やSMS、コミュニケーションツールによるチャットでの情報伝達も含まれます。建設現場では機械のリモート操作をしたり、VRやARによって現場の状況を可視化したりするICTの技術がDXに活用されています。
ディープラーニング
ディープラーニング(深層学習)とは人の脳がおこなっている機能を模倣して学習を進めるAIの一つです。画像認識や顔認証などの技術はディープラーニングに基づいて確立されています。建設業界では、例えばディープラーニングによる画像認識を使い、建設現場の品質管理を自動化するといったDXを実現できます。
建設DX化の進め方
DXで解決すべき課題を洗い出す
建設業界では課題が多い状況があります。建設DXの推進では課題解決の視点から進めていくことが合理的です。まずはDXで解決すべき課題を調査して把握することが不可欠です。現場のヒアリングをして人材不足などの課題を確認していきます。そして、DXに必要なデータを収集して蓄積するインフラがあるかも実態を調査します。
DXの目的を明確化する
調査結果に基づいて解決すべき課題を明らかにしたら、目的を明確にして共有します。建設DXではアナログ作業に慣れている従業員による協力を得て、全社的に取り組むことが必要です。目的を定めて、建設DXが実現されたときに何が変わるのかを示しましょう。取り組むメリットがわかると意欲的に取り組む気持ちが生まれます。
DX戦略を定めて具体化する
建設DXの目的が定まったらDX戦略を策定して計画を立てます。同じ課題でも解決する方法は複数あります。全体を俯瞰して課題解決が達成された後、どのように業務が進んでいるのが理想かを考えて戦略を定めるのが大切です。DXは段階的に進めていかないと現場の抵抗を受けることが多いので、段取りを考えて計画に落とし込むことが必要です。
インフラ構築から始める
建設DXはインフラ構築から始めて積極的に取り組める環境を整えることが大切です。スモールスタートから始めるのが基本ですが、その結果を次に生かせるようにするにはデータの蓄積や活用ができるインフラが必要になります。従業員が新しいDXの取り組みを始めたいと思ったときにすぐに取り入れられるようにするためにもインフラ構築を重視しましょう。
導入結果を検証して改善する
建設DXは長期的に取り組む必要があります。インフラやシステムを導入したら、効果検証をして改善点を検討することが大切です。最初から業務トラブルがなく、スムーズにDXができることはあまりありません。インフラの改善やシステムのカスタマイズ、業務フローの改定などを通して建設DXの目的達成に向けて進んでいきましょう。
建設DX化の際の注意点
現場を優先してDXを推進する
建設DXを推進するときには現場を優先しましょう。現場で建設の作業や管理を担当する従業員がいなければ、建設を担っていくことができません。建設業界での人材確保の困難さも踏まえて、貴重な人材を失わないようにDXの戦略を立てましょう。現場で働いている人たちにヒアリングをして、現場で作業をやりやすいようにするにはどうしたら良いかという視点で議論する場を設けると、協力しながらDXを推進できる下地を整えられます。
自社の課題に基づくDX化を進める
DXは自社にとって課題解決になることが重要です。建設業界の他社でDXに取り組み、課題解決に成功したとプレスリリースされることがあります。しかし、その内容を踏襲しても自社にとって最適なDXになるとは限りません。現場の状況もバックオフィスの業務状況も企業によって異なります。建設業のヒエラルキーでどの位置にあるかによって、取り組むべき課題が違います。自社にとっての課題を明確化してDX戦略を立てるようにしましょう。
競合との差別化を検討する
競合優位性は建設DXでは欠かせません。プロジェクトの公募があったときに、他社よりも優れている点を明確に示せれば採用される可能性が高くなります。元請け企業が下請け企業を選ぶときにも、競合他社に比べて技術的に優れているだけでなく、連携を取りやすいシステムを整備していれば有力候補になるでしょう。顧客からは常に競合他社と比較されることに注意が必要です。顧客から選ばれるように方向性を立てて取り組むことがDXにつながります。
建設DXの活用事例
竹中工務店
竹中工務店では建設現場における新しい生産のあり方をサポートするDXソリューションとして竹中新生産システムを開発しています。竹中工務店の取り組みとして建設ロボットプラットフォームがあります。BIMデータを地図情報として活用し、自動輸送ロボットや清掃ロボット、ドローンなどを自律移動させたり、遠隔操作したりすることが可能なシステムです。竹中工務店が開発してきたロボットを統合的に稼働させる高度化の事例です。
参照:ロボットの自律走行と遠隔管理を実現する「建設ロボットプラットフォーム」を開発|プレスリリース2020|情報一覧|株式会社 竹中工務店
小柳建設
小柳建設では複合現実(MR)によるリモートコミュニケーション・3次元データ投影ツール「Holostruction」を開発しました。HolostructionはMRによって3次元モデルや建設現場の投影ができるシステムで、タイムスライダーによって時間軸も設けて建設プロセスを視覚的に確認することが可能です。移動しながらでも図面や3次元データを見ながらコミュニケーションを取れるシステムになっているため、効率的なワークスタイルを実現できます。
参照:次世代コミュニケーションツール「Holostruction」
大成建設
大成建設ではAIとIoTを活用するDXインフラとして、メッシュWi-Fi環境に基づくDX基盤「T-BasisX」を構築しました。インターネット環境を建設現場全体に広げてデータの収集・取得・分析ができるようにしています。T-BasisXによってロボットやICT機器の活用が容易になりました。IoT活用見える化システムとの連携によって現場のカメラ映像のデータなども網羅的に一元管理できるようになり、安全監視や品質管理などにも応用しています。
参照:Wi-Fi環境とAI・IoTを一体化したDX標準基盤「T-BasisX」を構築 | 大成建設株式会社
関連リンク:【業界別・DX導入事例14選】DX成功事例に見るDX推進のポイントは?
建設業のDX化の第一歩は「SMS」から始めよう
DX化の波に乗って、コミュニケーション手段としてSMSを利用する企業が増えています。建設業では、工事の件で緊急に連絡が必要な事項が発生した際に、関係者一人ひとりに電話やメールで連絡するのでは迅速に指示を出せません。「電話に出てもらえなかった」「メールに気づいてもらえない」といったことが起こりやすく、連絡がつくまでの間は作業を停止せざるを得ないことが発生していました。DX化では関係者間での迅速なやりとりが大切です。携帯電話宛のSMS送信ならば、着眼率が高いため、メールよりも早く気づいてもらえるため、課題解決につながりました。
法人向けSMS送信サービスなら「KDDI Message Cast」
KDDIグループが提供するKDDI Message Castは、地方自治体、病院、不動産管理会社など、多数の企業で導入実績があるSMS送信サービスです。国内直収接続のため、到達率の高さで定評があります。料金未納者への督促など、手間やコストがかかっていた業務を改善することが可能です。初期費用、月額費用もかかりません。毎月利用した分だけ費用が発生する従量課金制もポイントです。SMSを有効に活用できるKDDI Message Castをぜひご検討ください。
まとめ
建設業界では、業界特有の課題解決として、DXに注目が集まっています。DXを導入することで、建設業で課題となっている人手不足、生産性の低さ、技術継承といった課題を解消できるでしょう。国も建設DX推進に向け、「インフラDX 総合推進室」を発足し、本格的にDX推進に取り組んでいます。アナログのイメージが強い建設業界では、AI、ドローン、3Dデータなどの先端技術を活用することにより建設業のDX化が進むことが期待されています。
その他のDX関連
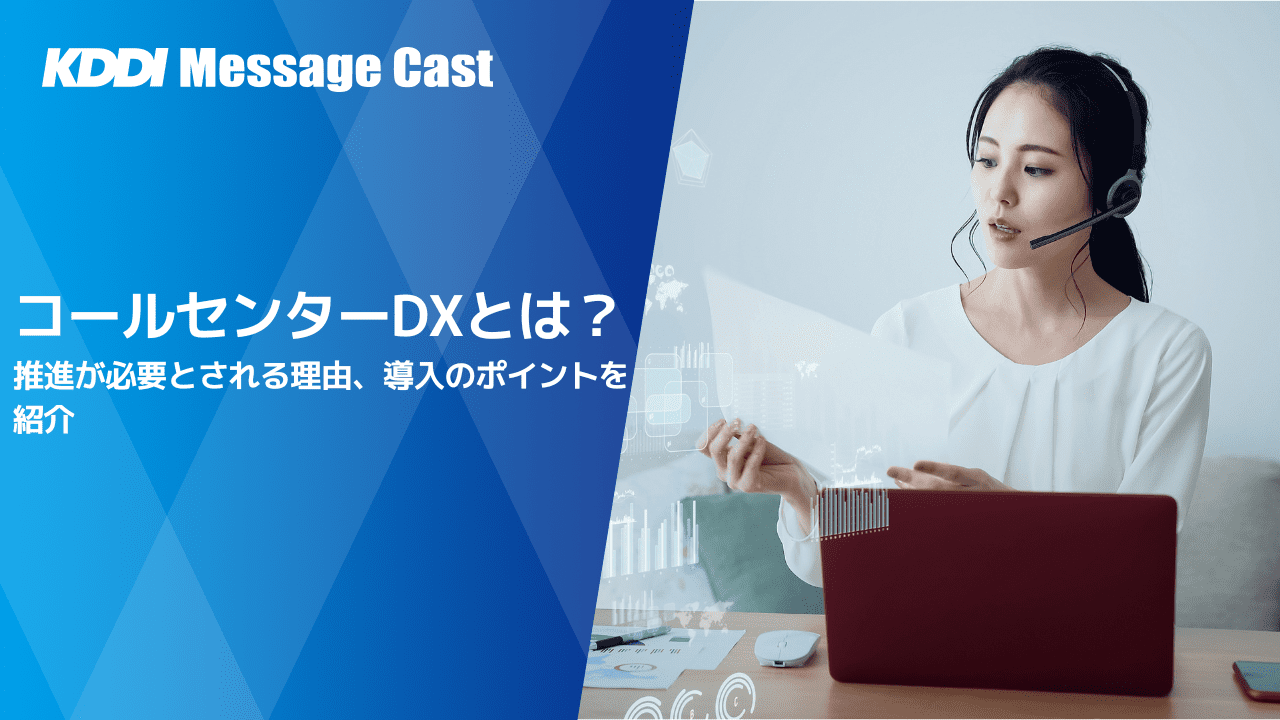
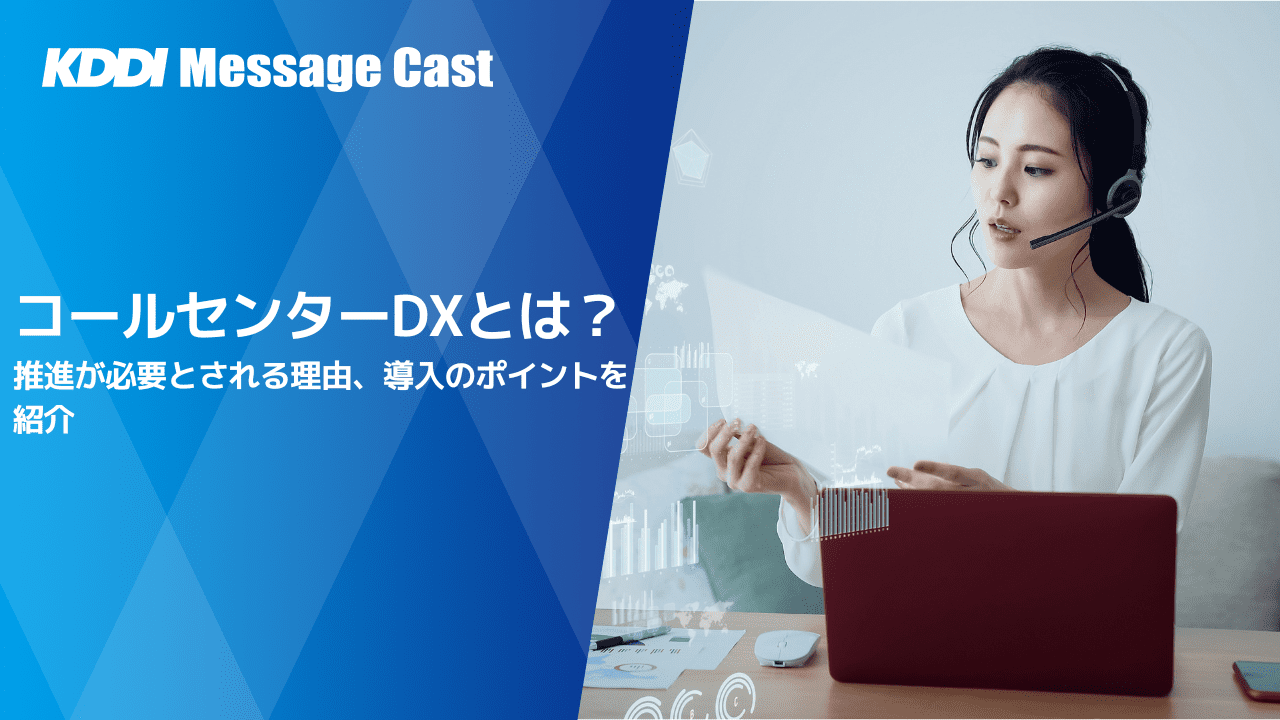
コールセンターDXとは?推進が必要とされる理由、導入のポイントを紹介


人材業界におけるIT化・DX促進とは?活用例も解説
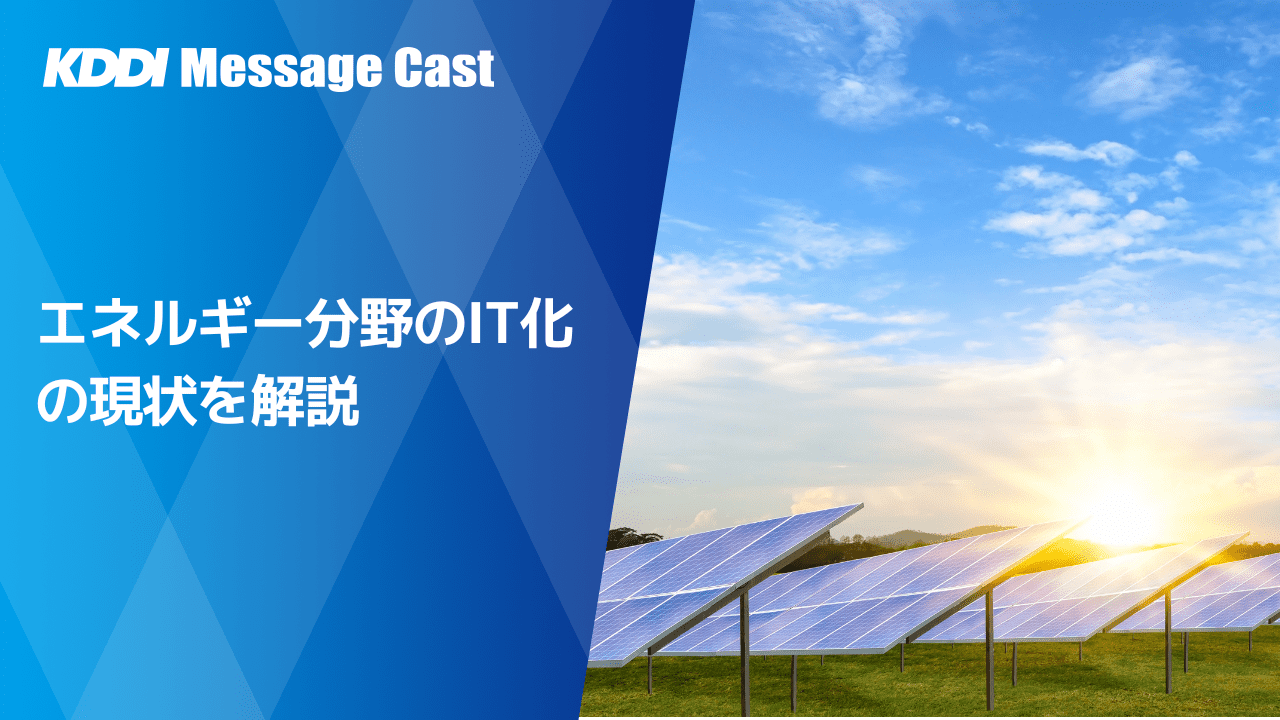
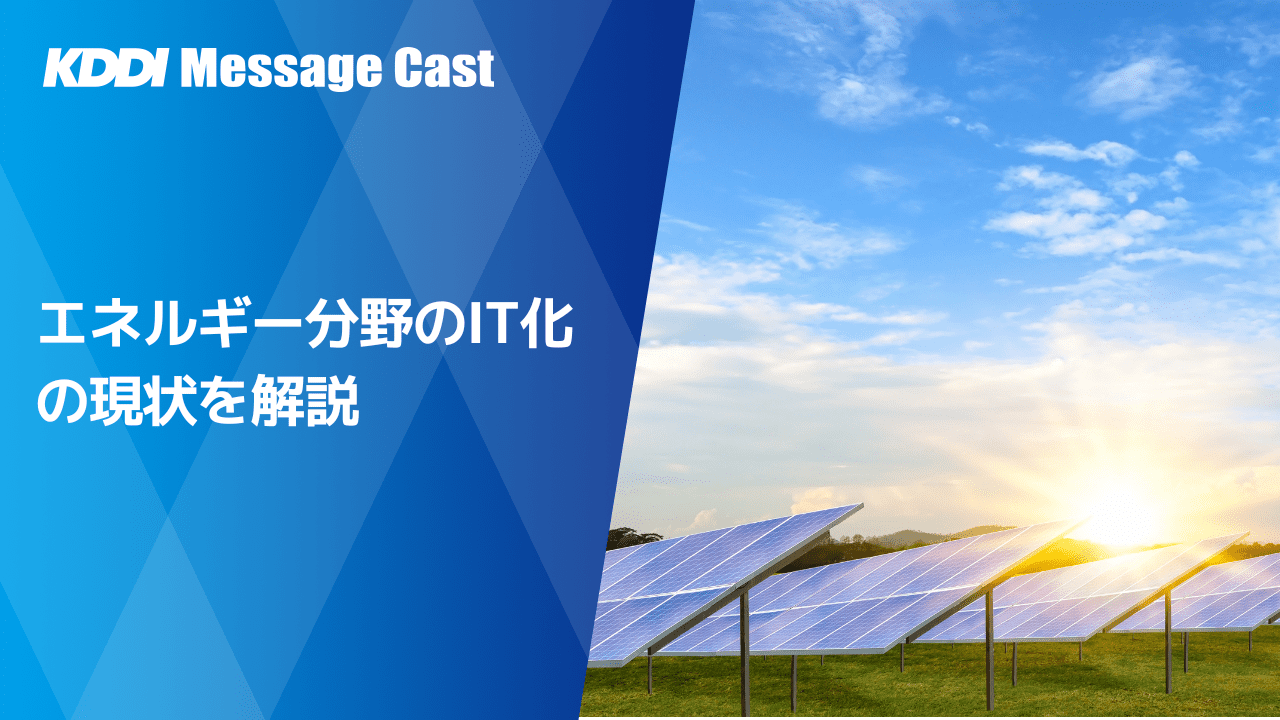
エネルギー分野のIT化の現状を解説


人材業界の業務を効率化して情報共有における課題を解決しよう


人材業界でペーパーレス化を進めるメリットやデメリットは?方法や成功事例を紹介