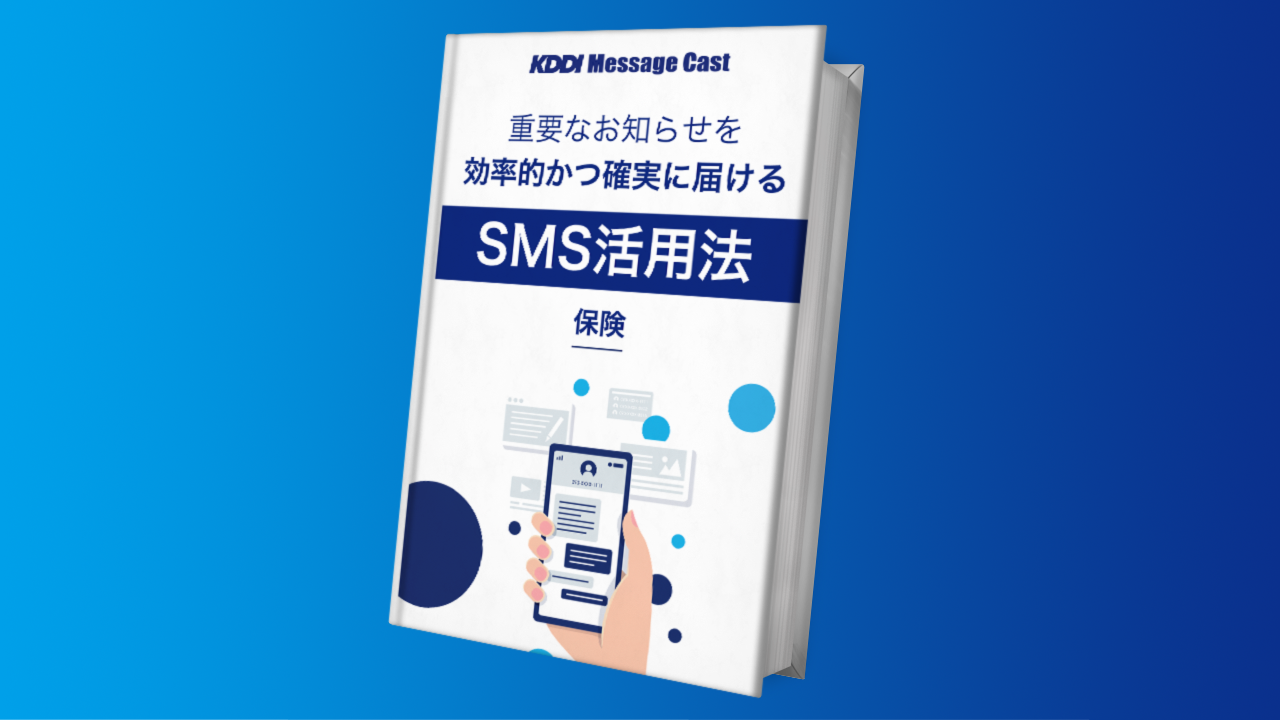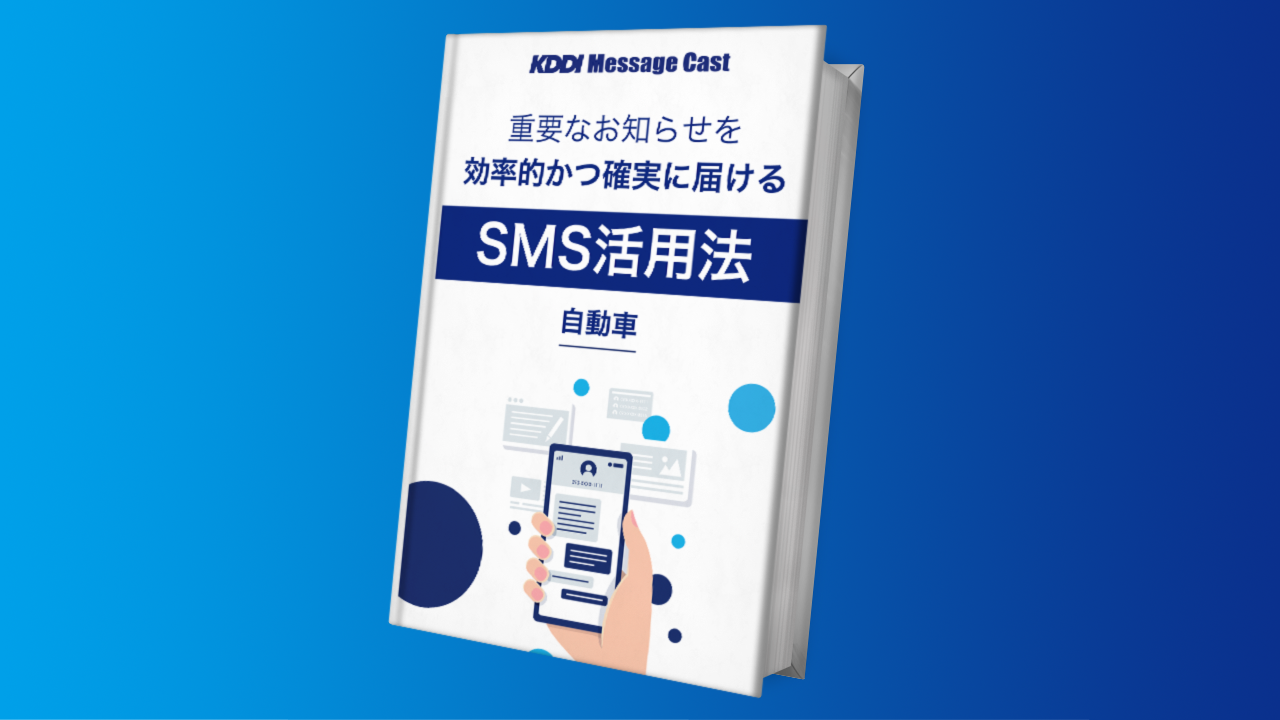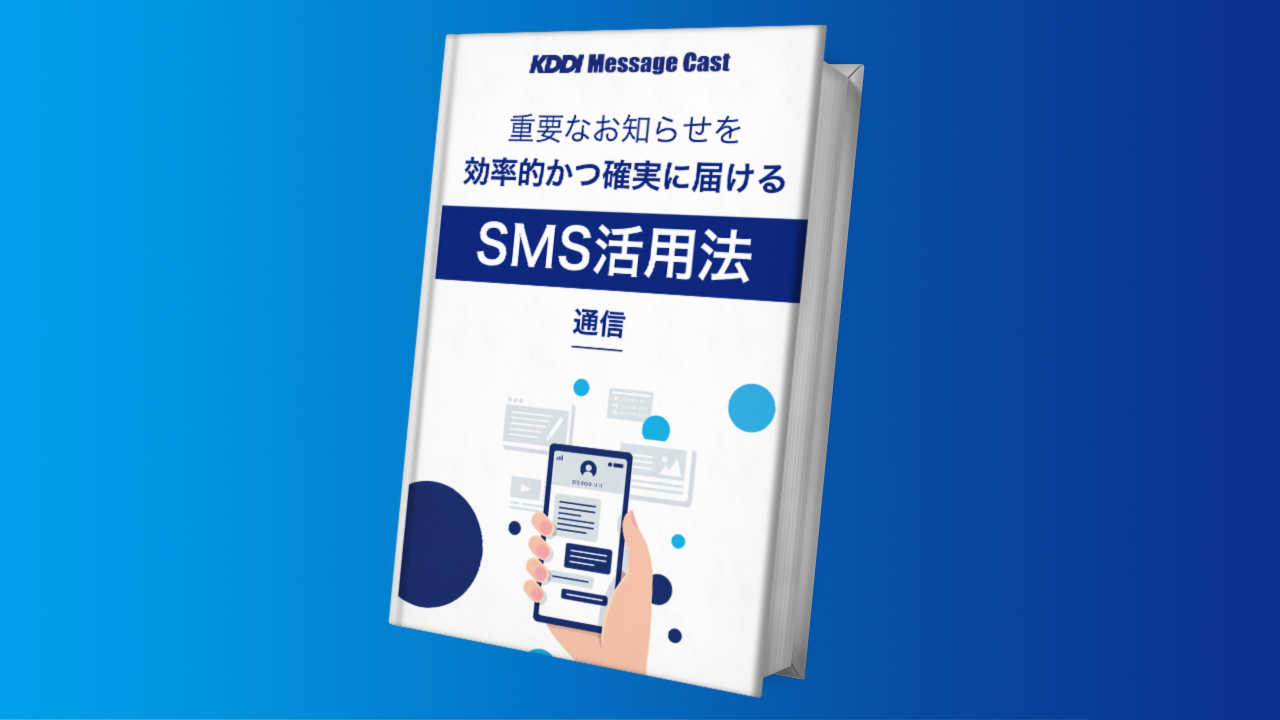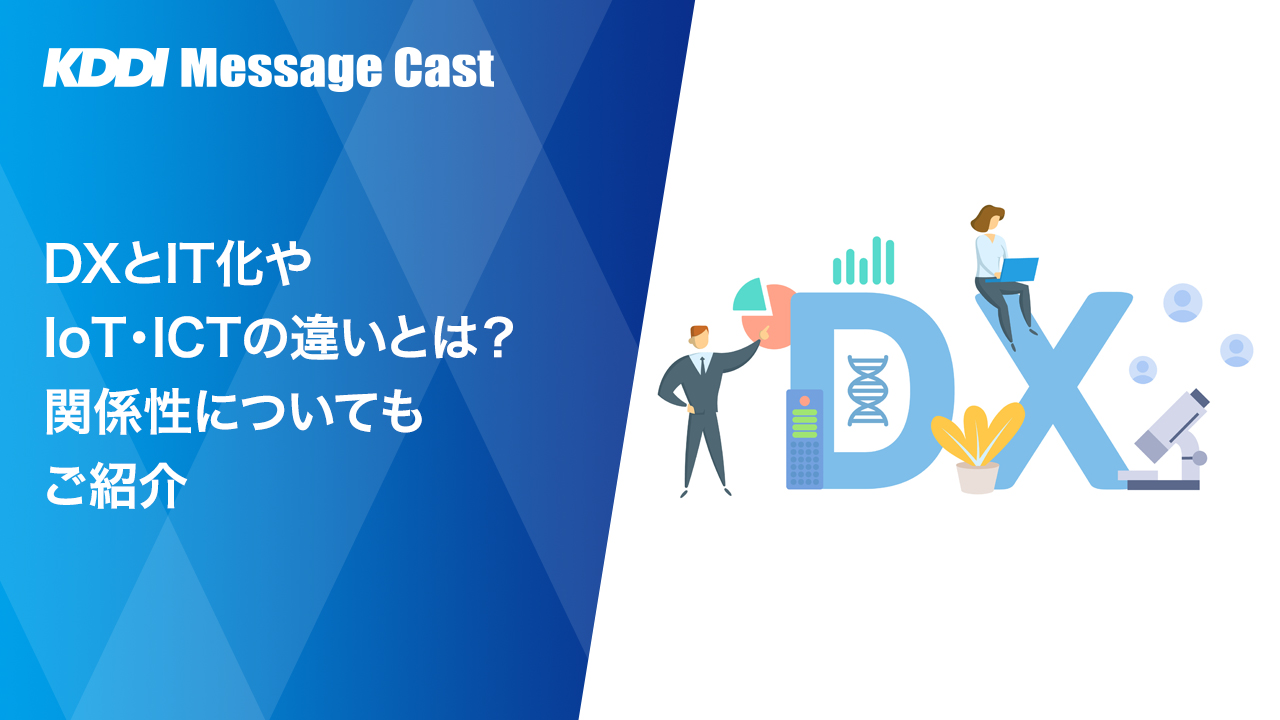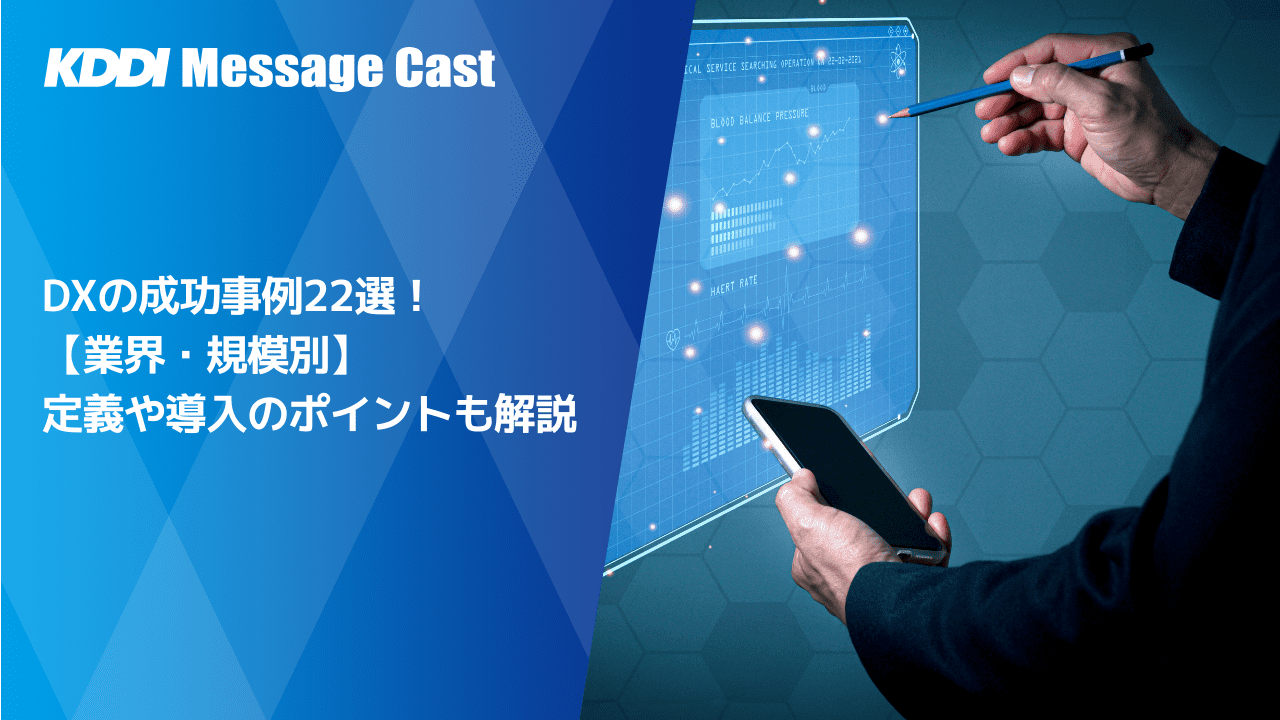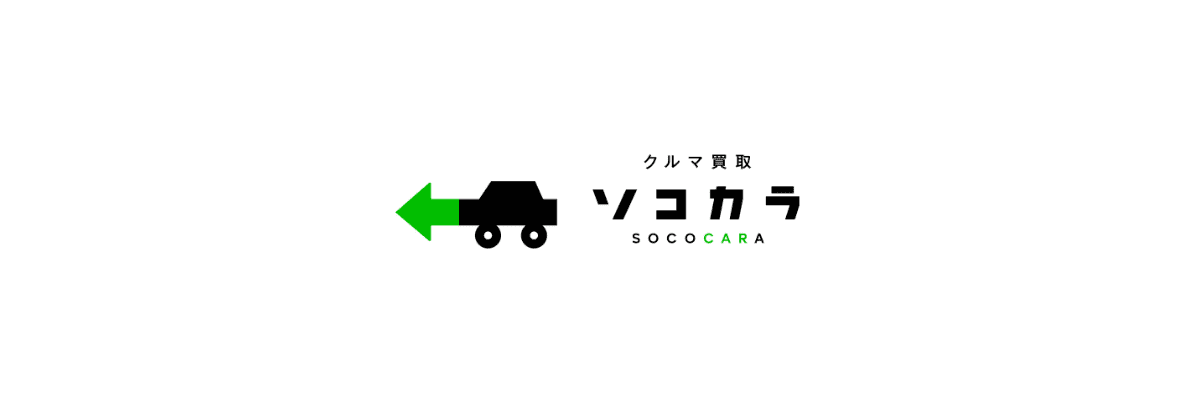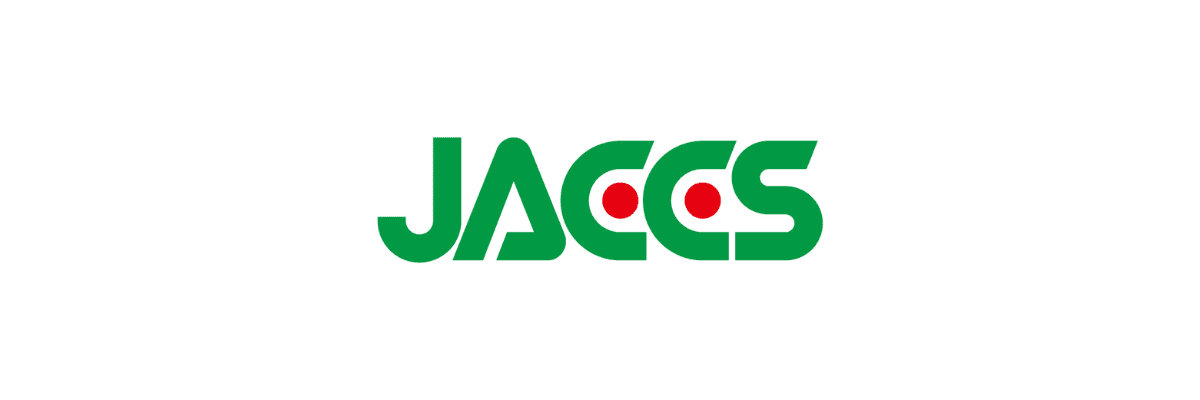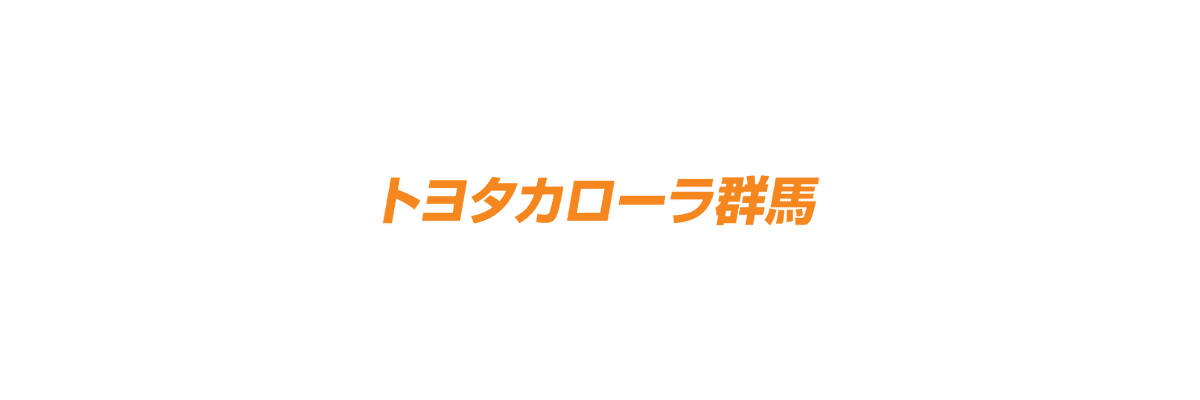自治体DXとは?目的、推進手順、具体的な成功事例を解説!


近年、自治体が抱える問題は深刻化しています。少子高齢化による人口減少などの影響を受け、従来のサービスの維持が困難となっている地域もあります。また、各職員が担当すべき業務量の多さが問題となっている地域も少なくありません。そうした中で、注目されているのがDXです。
本記事では、自治体DXとは何か確認した上で、自治体がDXを必要とする理由や自治体DXの先進事例などについて見ていきましょう。
目次
自治体DXとは何か


近年、国内のみならず海外においても多くの企業がDXの推進に力を入れ、自社の競争力を高めようとしています。こうした流れの中で、自治体においてもDXを推進していこうという動きがあります。
ただし、自治体の場合は民間企業と異なり自分たちの利益拡大というよりも、住民の利益を拡大することを目標にDXの導入を検討している傾向にあります。自治体はDXを推進することで、住民の利便性の向上や提供するサービスの品質向上を目指しているのです。
そもそもDXとは
DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略語です。デジタルの技術を使って、ビジネスや人々の暮らしを変えていくことを目標にしています。
日本においてDXが広まったのは2018年です。経済産業省が「デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン」を公表したことをきっかけに広く知られるようになりました。
社会にDXが普及することで、私たちの暮らしはこれまで以上に快適、かつ豊かになると期待できます。
DXについての詳しい記事は、以下をご覧ください。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?DX推進のメリットと課題も
自治体DXが必要とされる理由
現在、自治体が抱える問題は多様化、かつ複雑化しています。その背景には少子高齢化や地方公務員の減少などが挙げられます。
地方公務員のなり手が少子高齢化の影響などを受けて不足すれば、サービスをこれまでのように提供することや、自治体を運営する資金の確保が困難になります。その他にも、住民の居住エリアが散在すれば、インフラの修繕やゴミの収集が非効率となり、コストも割高になるでしょう。
また、近年は、若年層を中心に進学や就職をきっかけに都市部での暮らしを選択する人が増えています。多くの若者が都市部で就職し、地方公務員のなり手が不足すれば、既存の職員の負担増加や、住民に高品質のサービスを届けることが困難になると考えられます。
これらの問題を解決するには、デジタル技術による業務の効率化やコスト削減などが不可欠です。
自治体DX推進計画の重点取組事項


自治体DX推進計画とは、総務省が公表する自治体DX推進に向けた計画のことです。2021年1月から2026年3月を対象期間とし、自治体が重点的に取り組むべき事項や内容についてまとめられています。
情報システムの標準化・共通化
自治体における各種手続きのオンライン化や書類の保存、審査、決裁などの業務のオンライン化を目指しています。
多くの自治体が情報システムの独自活用などを既に進めています。2025年を目標に、選挙人名簿管理など主要な17業務(20業務)を処理するシステムの標準化・共通化を行うことで、システムの改修対応における自治体の負担軽減が可能になると見込まれています。
参照:自治体DX推進計画概要|総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000727132.pdf
基幹系17業務(20業務)
自治体情報システムは当初17業務を想定して標準化・共通化を進めていました。現在では印鑑登録、戸籍、戸籍の附票の3業務が追加されて以下の20業務が対象になっています。
- 住民基本台帳
- 選挙人名簿管理
- 固定資産税
- 個人住民税
- 法人住民税
- 軽自動車税
- 子ども・子育て支援
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 就学
- 健康管理
- 国民年金
- 国民健康保険
- 介護保険
- 後期高齢者医療
- 障害者福祉
- 生活保護
- 戸籍
- 戸籍の附票
- 印鑑登録
参照:自治体情報システムの標準化・共通化
https://www.soumu.go.jp/main_content/000817081.pdf
マイナンバーカードの普及
政府は、ほとんどの国民の手元にマイナンバーカードが将来的に行きわたることを目指しています。
マイナンバーカードの申請手続きや説明は職員によっては業務の大部分を占めることになるでしょう。そうなると、従来の業務に支障をきたしたり、申請手続きが多い時期にはオーバーワークになったりすることも懸念されます。
総務省はマイナンバーカードの普及を進めるために、個人番号カードの交付事務によって人件費や窓口の設置費用などを補助しようという姿勢を示しています。
参照:自治体DX推進計画概要|総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000727132.pdf
行政手続のオンライン化促進
マイナポータルからマイナンバーカードを活用したオンライン手続きの実現を目指しています。対象となる手続きは児童手当の請求や要介護認定の申請など、31の手続きです。
各種手続きをオンライン化することで、職員の業務負担を軽減できます。また、少ない職員数でも従来通りに業務をまわすこともできるでしょう。
住民側にとっても行政手続きのオンライン化はメリットがあります。手続きを行う際の負担を軽減できる他、短時間で手続きを完了させることもできます。
参照:自治体DX推進計画概要|総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000727132.pdf
AI・RPAの導入
自治体職員の業務効率化をAI・RPAを活用することで実現を目指しています。
AIは人工知能と称されるもので、人間に取って代わって業務を行うこともできます。一方、RPAでは業務の自動化をはかることが可能です。
職員が行っている業務をAIとRPAに任せることができれば、職員の負担は大きく軽減できることが見込まれます。
関連リンク:
DXとAIとの関係性とは?導入のポイントや成功事例などを徹底解説
https://sms.supership.jp/blog/dx/dx_ai_dounxyu/
DXの目的とは?DXの目的を定めるべき理由と具体的な目的の例を解説
https://sms.supership.jp/blog/dx/dxmokuteki/
参照:自治体DX推進計画概要|総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000727132.pdf
セキュリティ面の強化
近年、企業や自治体においてセキュリティに対する意識が高まっています。不正アクセスの手口などが複雑化しているため、情報資産を守るには強固なセキュリティ対策が不可欠です。
また、行政手続のオンライン化や職員のテレワークを推進する際にも、セキュリティの強化を忘れずに行わなければなりません。
参照:自治体DX推進計画概要|総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000727132.pdf
テレワークの実施
新型コロナウイルスの感染対策をきっかけに多くの企業が従業員の働き方をテレワークに切り替えました。一方、自治体ではテレワークは普及しにくい傾向にあり、出社を前提とした働き方をしている職員がほとんどです。
自治体においてもテレワークを導入できれば、コロナ禍でも職員は比較的安心して働けるようになります。また、育児や介護との両立も容易になると考えられます。
参照:自治体DX推進計画概要|総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000727132.pdf
自治体DXの推進における課題
課題1:地方公務員の職員数の減少
総務省「地方公共団体の総職員数の推移」によると、総職員数は1994年をピークに減少傾向にあります。2019年頃から微増しているものの、少子高齢化が深刻な問題となっている昨今において今後も職員数の減少は懸念事項になるといえるでしょう。
職員数が減少した際にも、住民に高品質のサービスを提供できるように、業務の自動化や効率化などを進めていかなければなりません。
参考:https://www.soumu.go.jp/main_content/000608426.pdf
課題2:デジタル人材の確保の重要性の向上
自治体でDXを推進するにはITやデジタル技術に精通している人材の確保が必要となります。
アナログ文化が残る自治体や最新技術に対して苦手意識を抱く自治体も多いです。既存の職員でITやデジタル技術に対応することが難しい場合は、高いITリテラシーを有する人材の確保が不可欠となります。
IT技術に精通した人材を採用することでDXをスピーディーに普及させ、住民にとって満足度の高いサービスの提供を短期的に実現できるようになるでしょう。
課題3:アナログ文化からの脱却の必要性の高まり
前述のように自治体の多くがアナログ対応を行っています。各種手続きを紙で行っていたり、データ入力など煩雑な業務を手作業で一つずつ行ったりしている自治体も多くあります。
手続きなどを紙で行っている場合、書類を管理するスペースが必要となる他、紛失のリスクについても考えておかなければなりません。
また、全ての業務を手作業で行っていると職員の負担は増大し、心身ともに疲弊してしまうでしょう。それだけでなく、住民へのサービスの品質低下や他の業務に手がまわらなくなることなども懸念事項となりえます。
課題4:DXに対する意識
2020年に総務省が自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画を公表したにもかかわらず、自治体ではDXに対する意識が浅い状況が続いています。DXの必要性についての理解が進んでいないのが原因です。公務員として、安定した身分が保証されており、変化する必要はないという意識を持っている人もいます。企業とは違って競争力を手に入れる取り組みは要らないと認識していて、DXに積極的に取り組む意識がない人も多いのが実情です。
参照:自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画|総務省
課題5:住民とのコミュニケーション不足
自治体が住民とのコミュニケーションを活発におこなっていないことも課題です。住民にとって快適な行政サービスを提供することは自治体の重要な役割です。DXは住民の利便性を向上させる目的で有効ですが、住民が何を不満に感じているかを自治体側が正しく把握できていない状況があります。マイナンバーカードの導入は、国の方針に従って一方的な行政を進めてしまっているケースとして有名です。住民から課題を聞き出して改善する気概を持つ風土を作ることが自治体DXの課題です。
自治体DXの推進にあたって取り組むべき事項
自治体DXの推進では上述の重点取組事項を参考にしながら、並行して取り組むべき事項があります。あらゆる住民が快適に過ごせる地域づくりをすることを命題として捉えて、以下の3つの観点からDXを推進していくと成功に向かえるでしょう。
地域社会全体のデジタル化
デジタル化を地域社会全体で進める取り組みから行うことがまず大切です。DXはデジタル化されたデータに基づいて進めていく必要があるからです。地域でサービスを提供している企業や団体と協力をしながら、公的な目的で利用できるデジタルデータを蓄積していきましょう。自治体として地域住民からアンケート調査を実施してデータとして整え、行政サービスだけでなくインフラにかかわる各種サービスにも活用していく基盤を整備することが重要です。
また、インフラ面も整えてデジタル化を促進することも大切です。公共施設でWi-Fiを利用できるようにしたり、スマホで行政情報を取得できるサービスを始めたりすることでデジタルに親しむ文化を構築できます。
デジタルデバイドの対策
自治体はDXを推進する際にデジタルデバイドの対策を並行して進めることが必要です。デジタルデバイドとは情報格差で、デジタル化のメリットを享受できる人とできない人の格差が生じることを指します。自治体DXによって新しく提供されたサービスがスマホアプリをインストールできる人しか利用できないとなると、スマホに慣れている人とスマホに慣れていない人との間に格差が生じます。
デジタルデバイドの対策として、新しいITツールの使い方を相談できる窓口を設けたり、ツールのプロバイダやNPO法人などに協力を求めたりする方法があります。誰もが平等にデジタル化の恩恵を受けられるようにする施策を講じていきましょう。
アナログ規制の見直し
デジタル庁では「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」を2022年に公表し、「構造改革のためのデジタル原則」の推進を図っています。アナログ的な手法を前提としている社会や自治体でのアナログ規制を見直すことは、意識改革にもつながる重要な取り組みです。以下のアナログ規制が代表的な7項目として挙げられています。
- 目視規制
- 実地監査規制
- 定期検査・点検規制
- 常駐・専任規制
- 対面講習規制
- 書面提示規制
- 往訪閲覧縦覧規制
デジタル原則に進むためにはアナログ規制に該当するものを改正して、デジタル化を進めることが効果的です。自治体で制定した条例や業務フローを確認して、デジタル化を妨げるリスクがある項目をなくしましょう。
参照:
デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン|デジタル臨時行政調査会
構造改革のためのデジタル原則
自治体DXを推進する手順
自治体DXは以下の手順を踏んで進めていくことが大切です。
- 1. DXの必要性の理解と意識合わせ
- 2. 課題のリストアップとDX方針の明確化
- 3. DX推進組織の構築と計画の策定
- 4. DX計画の実行と評価
1. DXの必要性の理解と意識合わせ
自治体DXでは意識が低い職員との意識合わせをすることが欠かせません。DXの重要性や必要性についての認識を全体で共有し、DXによってメリットを生み出す意識を持つ風土を醸成することが重要です。共通理解に基づいて職員が一丸になって行政サービスのイノベーションをするという方向性を作りましょう。職員を刺激し、構造改革を起こすための努力を意欲的に進める下地を整えることが大切です。
2. 課題のリストアップとDX方針の明確化
DXの人的基盤ができたらDX方針を明確にして具体化する段階に入ります。まずは住民の声に耳を傾けて解決すべき行政課題を調査しましょう。同時に自治体の中で業務負担になっている部分や効率が悪い業務などを洗い出して課題リストを作り上げます。そして、DXによって自治体のあり方をどのように変革するのかを検討します。全体方針を決めて必要事項をリストアップし、DXをスタートする基盤を作り上げましょう。
3. DX推進組織の構築と計画の策定
DX方針が定まったら組織編成をおこないます。体制整備は重要で、専門部署を設けてDXを推進することで円滑に進められます。DX推進組織の構築では、DX部門を作るだけでなく、DX部門と各部門との連携体制も整えることが必要です。連携も含めて組織体制を構築しましょう。中心に立つDX人材がいない場合には人材獲得をすることも重要です。体制を整えながら具体的なDX計画を策定し、予算を立てて推進できる状況を作り上げます。
4. DX計画の実行と評価
体制が整ってDXのスケジュールや予算が策定できたら、計画に従ってDXを実行していきます。基本的には計画通りに進行させることを重視してDXを推進しましょう。ただ現実的には想定通りにならないこともよくあります。計画実行をしたら評価をおこない、必要に応じて方向付けを変更して理想の自治体DXを実現できるように着実に進めていくことが重要です。観察と評価のプロセスを経て行動に起こすOODAのフレームワークを重視すると成功しやすくなります。
自治体DXを成功させるためのポイント
ポイント1:小規模スタート
DXに取り組む際は小規模から始めましょう。導入段階から大規模に取り組むと、地域住民の混乱を招くことにもなりえます。問い合わせが殺到し、職員の業務に支障が生じることもあるでしょう。
また、職員も慣れない業務への対応が困難になることも推測できます。オーバーワークとなるほか、住民に安定したサービスを提供できなくなることも懸念されます。
ポイント2:体制構築
自治体でDXを推進するには体制の構築が不可欠です。部門や組織ごとに実施した場合、手続きが統一されずに連携を取ることができず、業務を円滑に進めることが難しくなるでしょう。
職員の中に状況を理解できていない人がいる場合、トラブルが生じた場合に住民に納得してもらえるよう説明できない可能性もあります。
利便性向上のために導入したDXが混乱の原因とならないためにも、体制構築をしっかりと行うことが前提です。
ポイント3:デジタル人材の育成
自治体の中にはアナログ文化が根付く自治体も少なくありません。そのため、既存の職員だけではDXを進めていくことが難しいケースもあるでしょう。AIやRPAの活用には高度な知識が求められるため、これらの知識を有する新たな人材を採用する必要もあります。
また、近年ではIT人材の不足が問題となっており、需要に対して供給が追い付いていない状況です。そのため、優秀なIT人材を新たに迎えるにも応募が集まらないこともあります。新しく雇い入れることが難しい場合は、IT関係の学部を出た職員やデジタル技術を得意とする既存の職員にDX推進に携わってもらえるよう育成することも検討しなければなりません。
ポイント4: DX計画の策定
DXに取り組む際は実施する事柄の内容や期間を明確にすることが不可欠です。計画を策定せずに曖昧な状態で行っていてもうまくいかないことがほとんどでしょう。
また、策定したDX計画は職員間でのみ共有するのではなく、住民に対してもDXを推進していこうと考えている旨やその計画を共有する必要があります。住民からの理解を事前に得ておくことで、導入をスムーズに進められます。
自治体DXの取り組み事例を紹介
事例1:三重県「スマート人材育成事業」
三重県ではスマート改革を推進するために、行政や社会全体のDX推進を牽引していく職員の育成が重要であると考えています。そこで、スマート人材育成事業という研修を2020年から開始しました。この研修の対象となるのはスマート改革を牽引する人材になる意欲をもつ若手職員です。
研修やセミナーで扱われたテーマはDXやICT、企画立案、予算化、プロジェクトマネジメントなどです。開催形態として、Web会議システムを活用するなど、近年主流となっているオンライン形式が一部採用されました。
参照:
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000936225.pdf
https://www.pref.mie.lg.jp/saiyo/29473027196-01.htm
事例2:大阪府豊中市「とよなかデジタル・ガバメント宣言」
豊中市はコロナ禍をデジタル技術の活用を進めていく新たな契機として捉えました。とよなかデジタル・ガバメント宣言では、豊中市の「暮らし・サービス」「学び・教育」「仕事・働き方」を大きく変えていくことが目標とされています。
この宣言に関係して、市民や事業者が市役所に足を運ばなくても手続きなどを行えるオンラインサービスの拡充も予定されています。
参照:https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/denshi/denshi_jichitai/digitalgovernment.html
事例3:東京都世田谷区「せたがやPay」
東京都世田谷区はデジタル地域通貨プラットフォームであるMoneyEasyを活用した地域通貨「せたがやPay」を発行しました。
せたがやPayはスマートフォンなどにチャージすることで使用でき、区内の店舗などでQRコードを読み取ることで決済できます。区では、決済額の30%相当をポイントとして付与するキャンペーンなども展開されました。
せたがやPayには住民の買い物が容易になるだけでなく、紙の商品券の発行でかかっていた経費を大幅に削減できるというメリットもあります。
自治体DXに活用できる補助金・助成金制度
自治体DXではデジタル基盤改革支援補助金を活用できます。マイナンバー制度の導入に伴い、マイナポータルや自治体の基幹システムの連携による行政サービスの提供が重要になりました。デジタル基盤改革支援補助金はクラウドによる標準準拠システムに移行して基幹システムを整えるための経費の補助を受けられる制度です。デジタル基盤改革支援補助金はマイナポータルや自治体の基幹システムに接続することを条件として支給されます。
自治体DXではIT導入補助金や事業再構築補助金などの補助金制度を活用して事業者に協力を促すことも可能です。資金不足でDXに協力するのは難しいと考えている企業や団体を巻き込む手段として補助金・助成金制度を活用しましょう。
参照:総務省|自治体DXの推進|自治体の行政手続のオンライン化
関連リンク:DXに活用できる補助金・助成金とは?申請方法や注意点などについて
自治体DXの推進にはSMSの活用がおすすめ


DXの推進を検討している自治体にはSMSの導入がおすすめです。SMSをうまく活用することで、住民に情報をリアルタイムで届けられるようになる他、コスト削減にもつながります。
SMSの活用事例として、税金に関する連絡が挙げられます。国民年金や住民税の入金案内や滞納連絡にSMSを活用することで、封書で連絡するよりも反応を得やすいだけでなく、郵送料金がかからないといったメリットを得られます。
その他にも、自治体主催のイベントや検診などの案内にもSMSは効果的です。郵送やポスターでは集客が難しいことも多いですが、SMSは受け取り手の目に留まりやすいため気付いてもらいやすいでしょう。また、開催日前にメッセージを再送することで、参加を促すことができます。
SMSを上手く活用することで、地域の活性化や住民の利便性向上につながると期待できます。
法人向けSMS送信サービスなら「KDDI Message Cast」
KDDI Message Castはお客様にSMSでメッセージを送ることを検討している企業におすすめできるサービスです。このサービスを活用することで、SMSをお客様に手軽に送れます。キャリア品質の保守運用体制のため、安全な配信を実現しています。また、異なるエンドユーザーへの誤配信のリスクも軽減できるため、大切な個人情報の漏洩防止にも効果的です。
まとめ


自治体が抱える課題の解決にはDXの導入がおすすめです。本記事で解説したように、DXを導入することで人口減少の影響による問題の解決や自治体で働く職員の業務負担軽減などにつなげることができます。自治体がDX推進に成功するには抱えている問題を明確にした上で、効果が期待できる方法を選択しなければなりません。DXと一口でいっても、さまざまな方法があるだけでなく、国から補助金の対象となるものもあります。自分たちだけで選択が難しい場合はコンサルタントに相談してみてもよいでしょう。
▼KDDI Message Cast(KDDIメッセージキャスト)詳しくはこちら
その他のDX関連
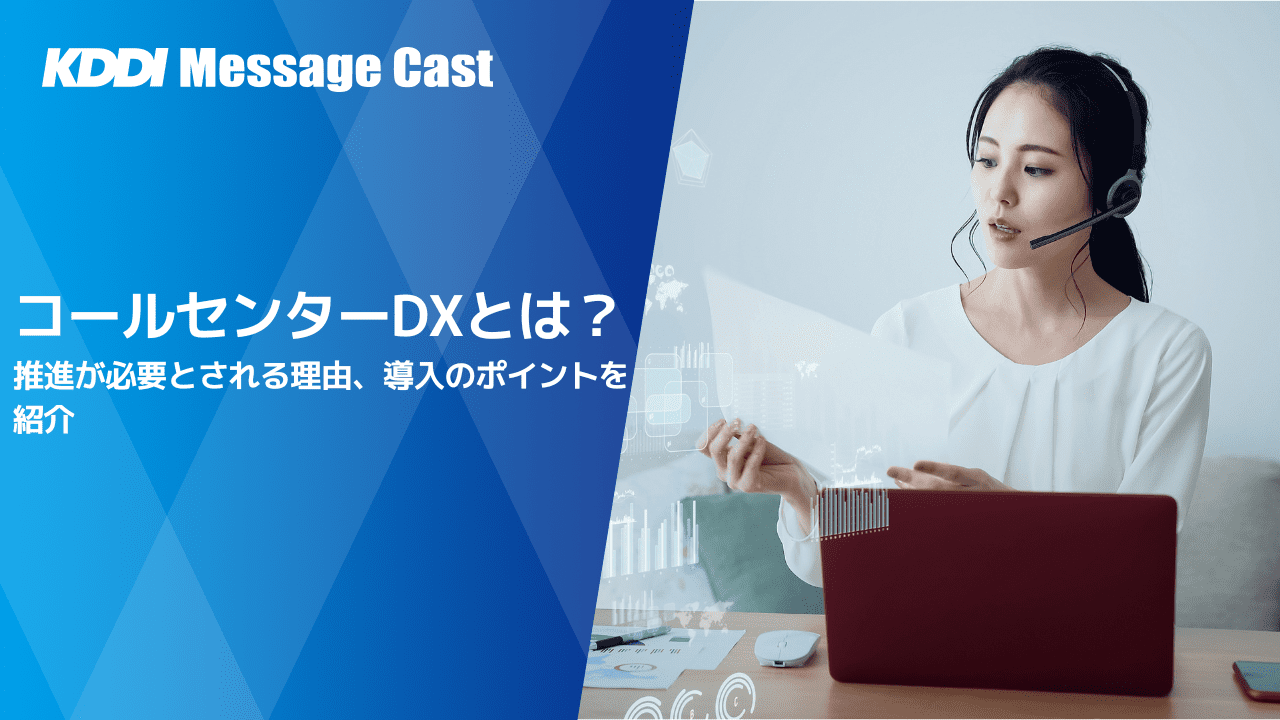
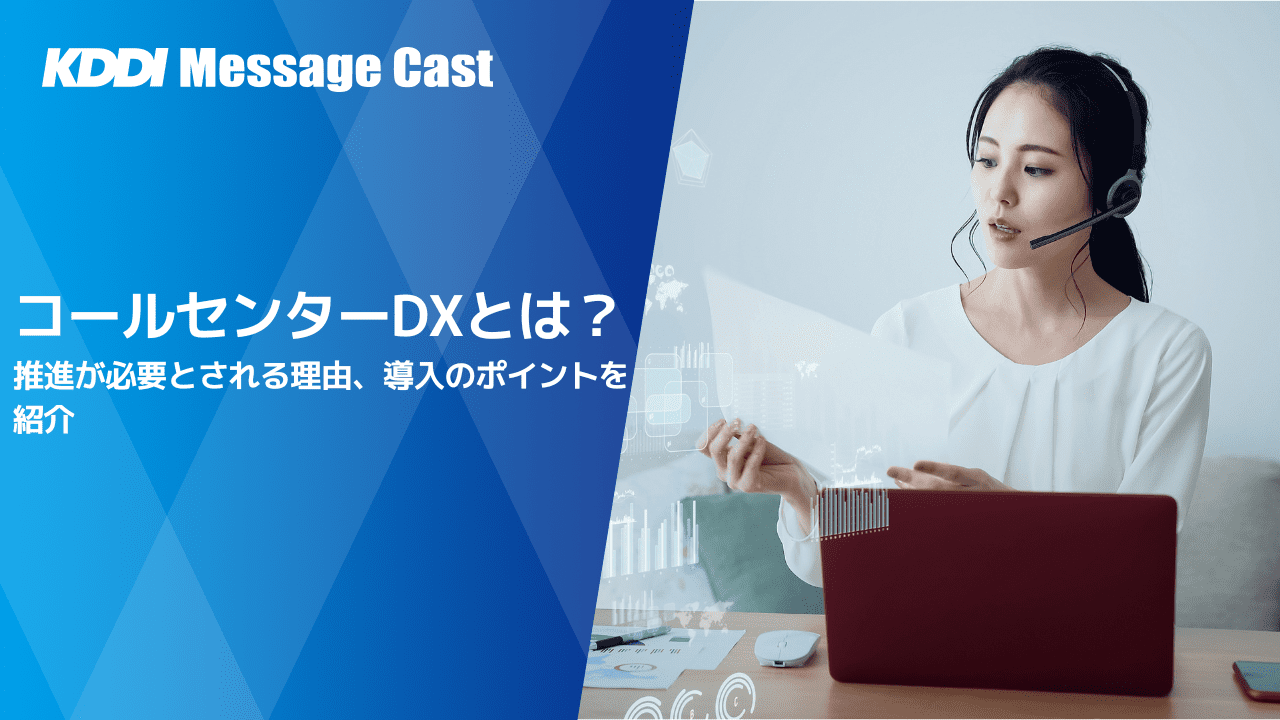
コールセンターDXとは?推進が必要とされる理由、導入のポイントを紹介


人材業界におけるIT化・DX促進とは?活用例も解説
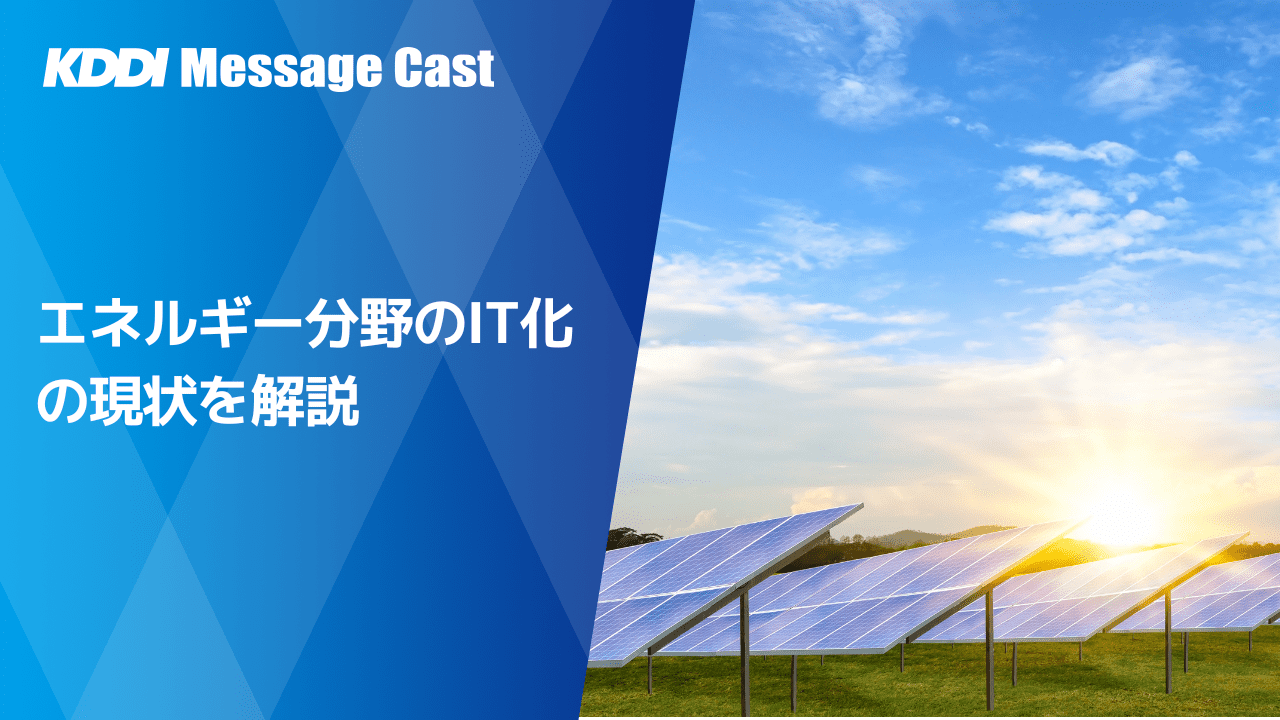
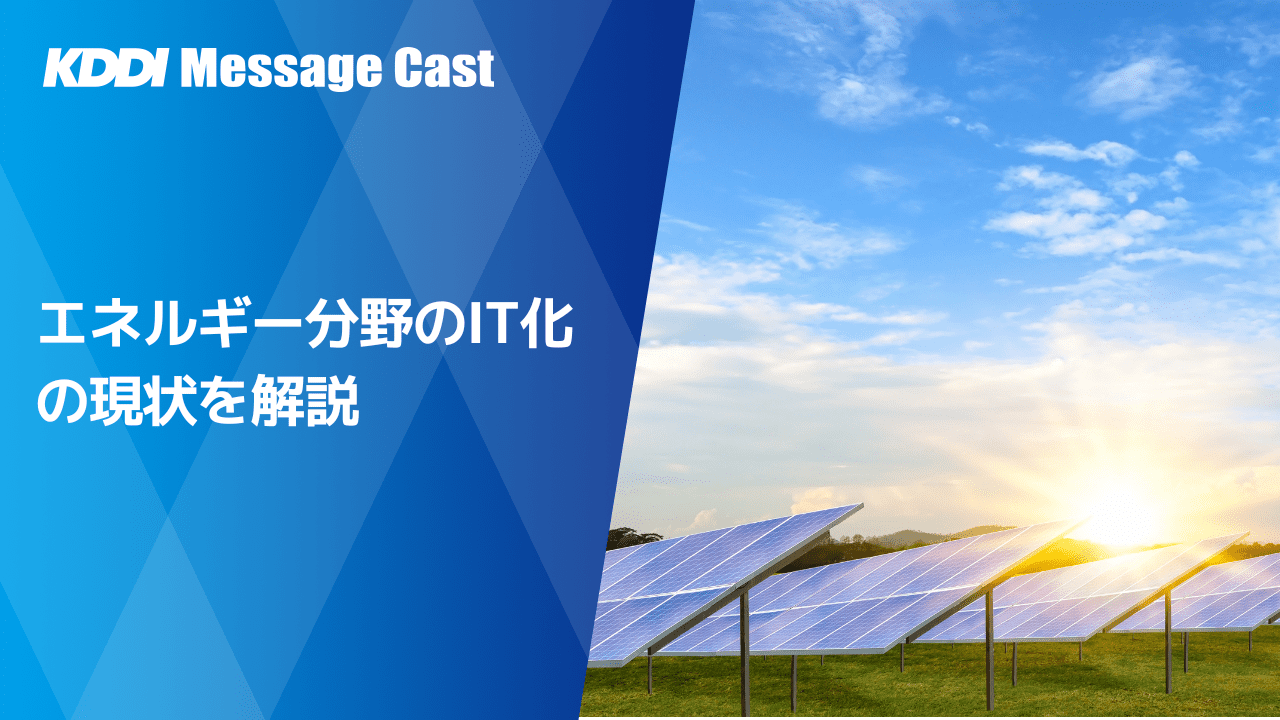
エネルギー分野のIT化の現状を解説


人材業界の業務を効率化して情報共有における課題を解決しよう


人材業界でペーパーレス化を進めるメリットやデメリットは?方法や成功事例を紹介