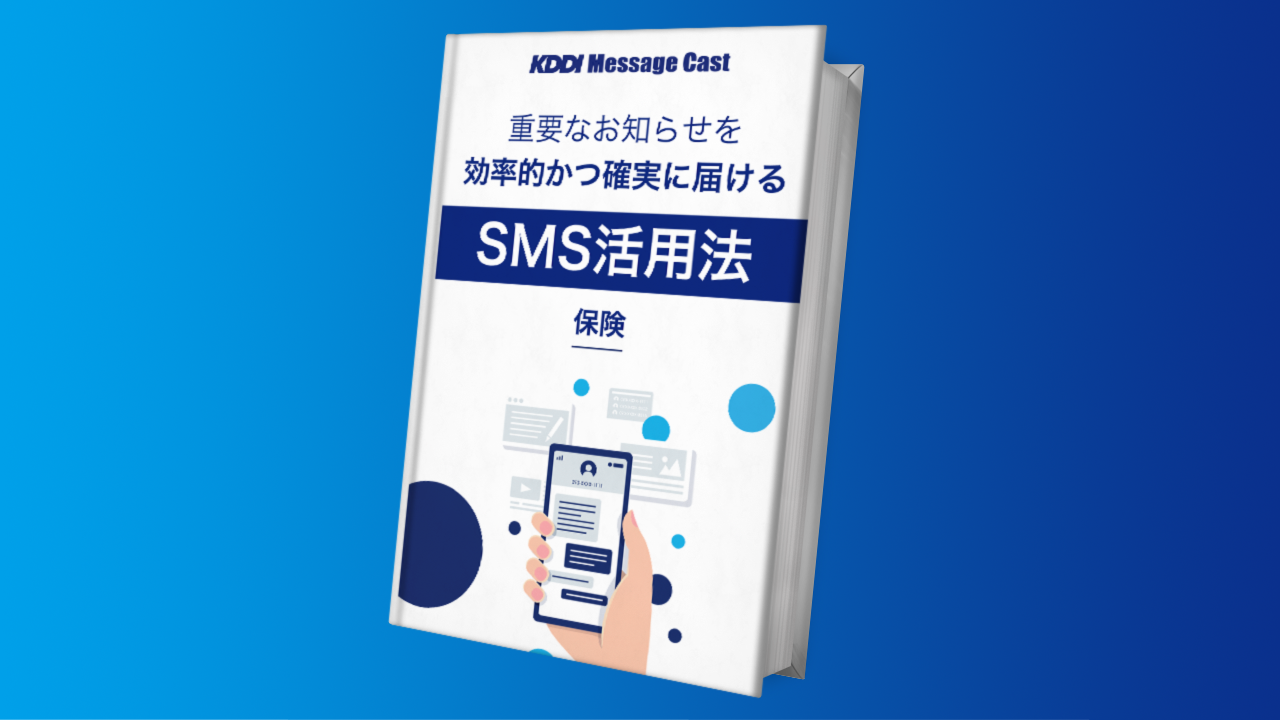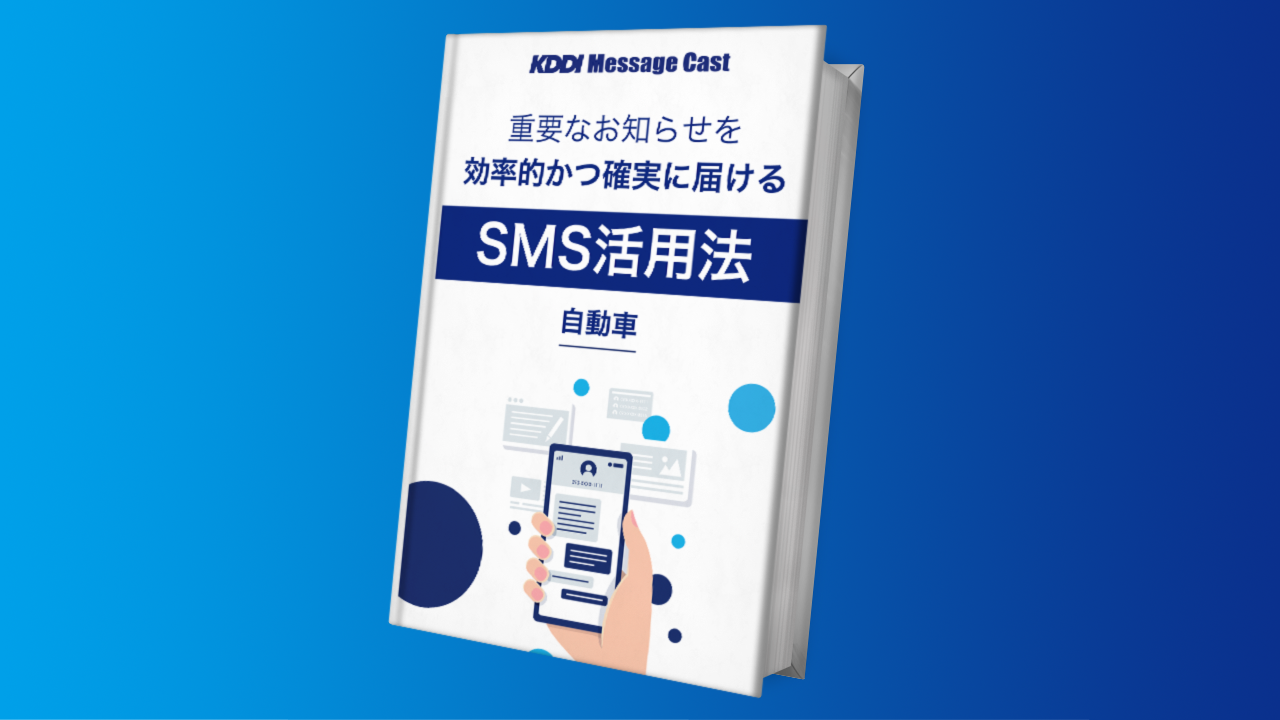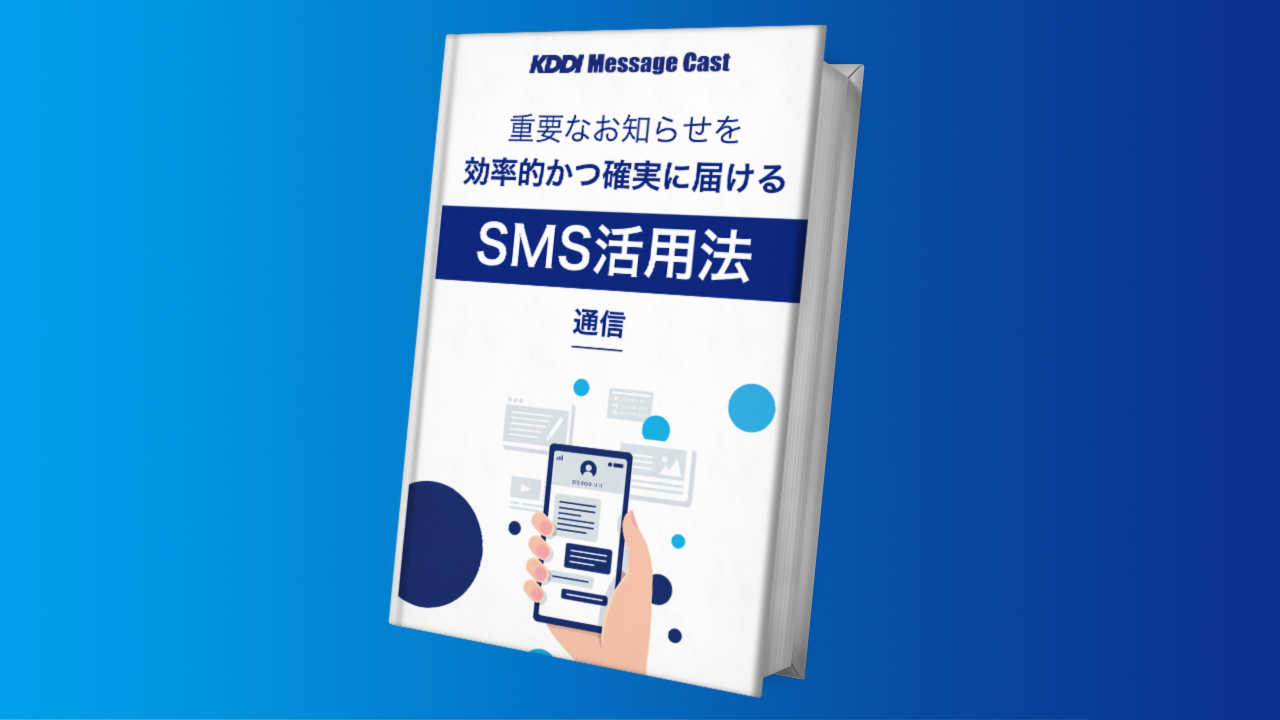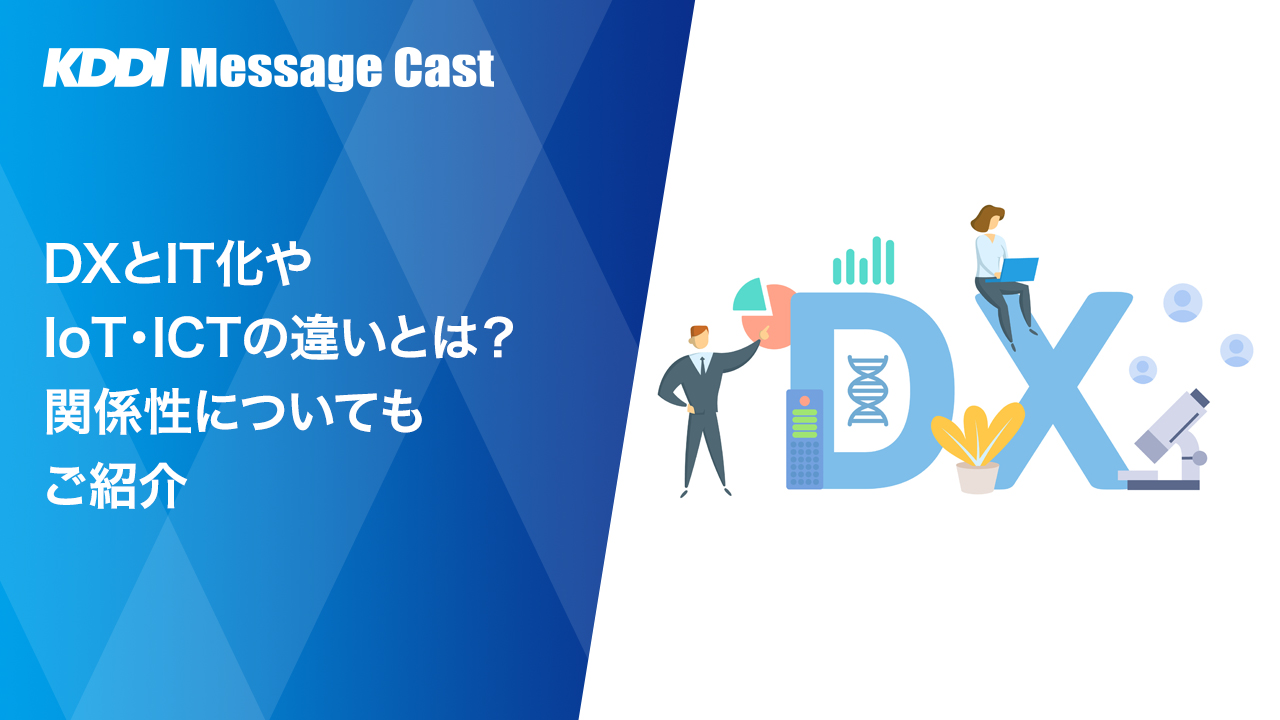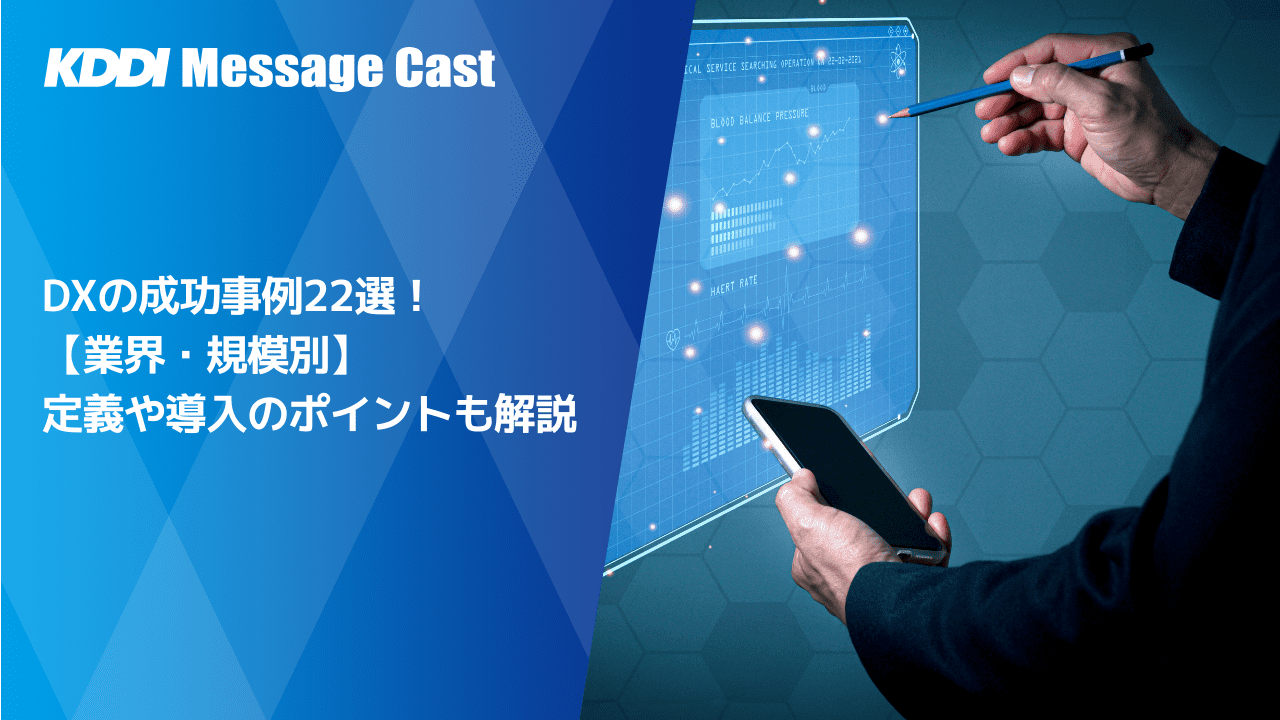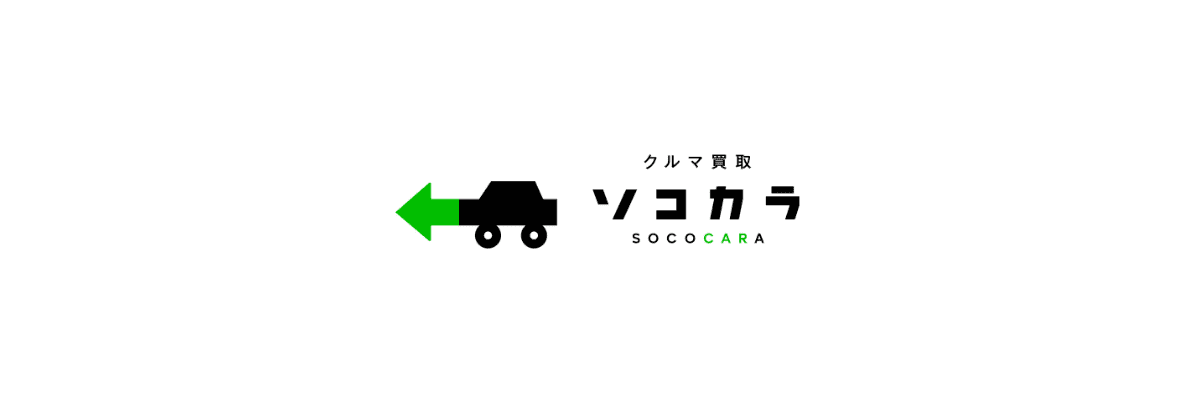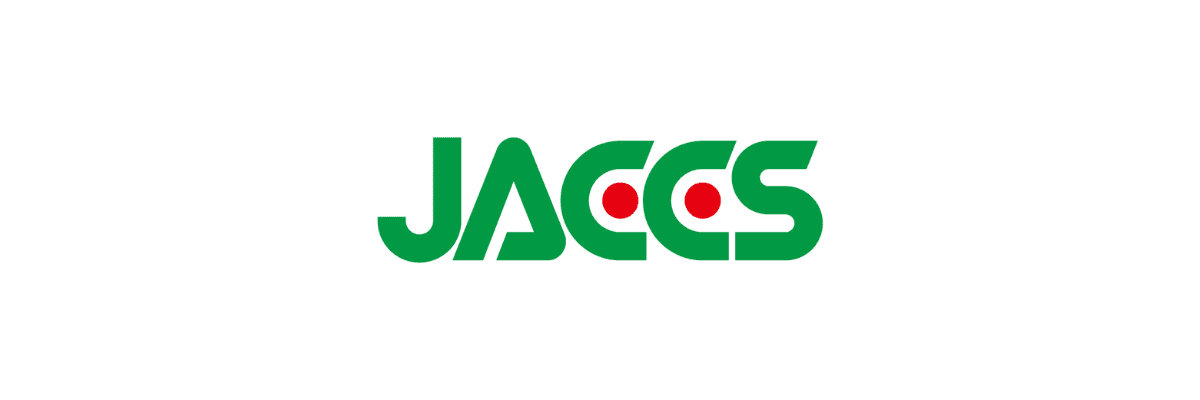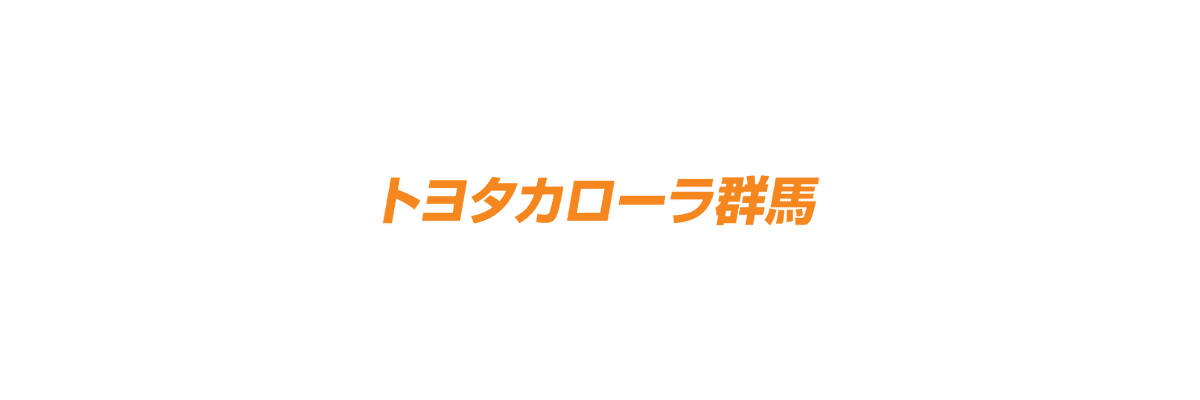製造業DXとは?課題、メリット、導入までのプロセス、成功事例について徹底解説


IT技術の発展と時代の変化に対応するため、各業界でDX化が注目されています。製造業のものづくりの現場でも、生産性アップやコスト削減の実現に向けて、ITソリューションの導入が加速しています。デジタル化の進化についていくために、製造業DXは欠かせないテーマです。しかし、DXを進めようとしても、さまざまな課題が伴います。本記事では、製造業DXの課題、成功させるためのポイント、推進プロセスなどについて解説します。
目次
製造業DXとは?
製造業のものづくりの現場でも、コスト削減や生産性向上の実現に向けて、デジタル化が加速しています。製造業におけるDXとは、デジタル化を促進することで、業務効率化を図り、製品を利用する人の生活がより良いものになるように変革していくことです。具体的には、例えば製造工程の全体を電子データで一元管理することで、現場の効率化がアップします。データ化による管理に伴い、既存のノウハウやブラックボックス化していた技術を蓄積できるようになり、情報の共有が容易になるでしょう。DXはアナログ作業が多い製造業の成長を助けることが見込まれ、多数の企業が注目しています。
DX化に成功しているのは、大手企業だけでなく、製造業を営む中小企業でも成功事例が多数あります。具体事例としては、株式会社今野製作所は、業務プロセスや社内の連携体制などを「見える化」しました。その結果、製品が製造されていく工程が把握しやすくなったことで、プロセスの最適化やシステムが導入しやすくなり、売上高が一気に2倍になったそうです。
参照元:製造業DX取組事例集
そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か
DXとは、デジタル技術の活用により、業務フローの改善をはじめ、ビジネスモデルの創出、さらには既存のシステムからの脱却、企業風土の変革まで、根底から覆すようなイノベーションを実現させることです。変化の激しい現代、市場で競争優位性を保っていくために、DXはあらゆる企業にとって重要なテーマといえます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?DX推進のメリットと課題も解説 – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」
製造業ではDXの推進をしなければ今後が危ういと考えられる状況になっています。DXは、国が推進している取り組みの一つです。政府はものづくりの技術振興に向けた施策に関して、「ものづくり白書」を公開しました。環境変化に対応するためには、企業の経営者や組織の能力が重要であり、経営資源の再構成や再結合に必要な能力の強化にデジタル化が有効であると言及しています。
また、産業界におけるDX推進は、企業の成長戦略であり、企業でDXが進まない理由として、デジタル技術に関連する知識不足、社内IT部門と他部門との対話不足を挙げています。製造業はものづくりの中心軸を担っている業界です。デジタル技術の取り入れに積極的に取り組み、DXを実現しなければ他社との差別化できる強みを発揮して生き抜いていくのが難しい時代になっています。
製造業DXの推進で実現できることやメリット
製造業でDXが企業の存続を揺るがすような状況になっているのは、製造業ではDXによるメリットが大きいからです。DXによって得られるメリットとして代表的なものだけでも以下のようにたくさんあります。
- 生産性の向上と管理体制の強化
- 見える化によるコストの削減
- 価値創造
- ダイナミック・ケイパビリティ志向の定着
- 人手不足の解消
DXを推進することで製造業が実現できることは多岐にわたっています。企業として抱えている課題を解決する手段としてDXは魅力的な方法です。ここでは5つの観点から製造業がDXに取り組むメリットを解説します。積極的なDX推進によって実現できることを理解して、必要な角度からDXを進めていきましょう。
製造業においてDXが重要視される理由


製造業においてDXの推進が重要視されるのは、生産性の向上やコスト削減、価値の創出などが理由です。それぞれについて解説します。
生産性の向上と管理体制の強化
製造業では、生産効率の向上は重視すべき点です。IT技術の導入やロボットの活用により、現場で全自動または半自動化が実現できます。その結果、人的リソースの大幅な削減が可能になるだけでなく、生産性の向上も期待できます。製造業ではいまだに紙媒体での記録の管理が多いですが、デジタル化は生産効率の向上に重要な役割を担うでしょう。ペーパーレス化に伴い、現場で収集したデータを活用することで、管理の体制の強化も図ることができます。製造現場をDX化すると、データに基づいた施策を講じられるからです。
見える化によるコストの削減
設備メンテナンスは、これまでは基本的に設備に何らかの異常事態が起きてから対応するか、メンテナンスの実施時期を決め定期的なチェックを実施するかのどちらかの方法でした。しかし、IT技術を活用すれば、異常状態を事前に把握できるため、早急に対応することができます。事前防止のメンテナンスが実現できれば、設備のメンテナンス費用の削減が可能です。
価値創造
DXは業務フローをはじめ、さまざまなビジネスの事象をデジタル化することですが、単にデジタル化するだけでは企業利益に寄与できません。従来はなかったデータを収集し活用することで、価値の創造につなげることが目標です。そのため、DX推進の本来の意義は、新しい価値を作り出すことにあります。最新のIT技術や機械の導入やロボットを活用することで、製造現場の最適化が実現すると、リソースに余裕がでてくるため、新製品の開発に時間とコストをかけられるようになるからです。価値の創出だけでなく、リソースを品質向上にも使うことで顧客満足度の向上も期待できます。
ダイナミック・ケイパビリティ志向の定着
ダイナミック・ケイパビリティとは環境に応じて柔軟に対応して動的に自社の強みを生み出していく力です。自社の機会や脅威を感知し、社内外の可能性を補足して新しい可能性を導き出し、変容させることがダイナミック・ケイパビリティです。
製造業では企業としてDXに積極的に取り組むことでダイナミック・ケイパビリティ志向が定着します。ダイナミック・ケイパビリティ重視の企業になれば、自然にイノベーションを起こして成長していけるようになります。
ダイナミック・ケイパビリティがあれば製造業ではDXによる変化の大きい現代に柔軟に対応できます。DXを通して自社の対応力を強化すれば、他社の動向に大きく揺るがされることなく事業を進めることが可能です。
人手不足の解消
DXは製造業における人手不足の課題を解消することにつながります。デジタル技術の導入によって、人の手でおこなってきた作業を自動化すれば少ない人数の従業員でも製品を製造可能になるからです。例えば、ロボットを導入して手作業で作っていた製品をロボットに製造させたり、人の目でおこなっていた検品をセンサーでできるようにしたりすれば、人手を減らしても生産できます。
生産管理システムを導入して効率化することも可能です。製造プロセスのデータをシステムで一元管理して分析すれば、無駄のない生産プロセスの設計や人材の配置ができるようになります。人材配置の最適化は人手不足の解消に特に重要なポイントです。余剰の人出がかけられている業務から他の業務に人材を配置変更することで、人手不足の状況を改善できます。
経済産業省の後押し
DXは、国が推進している取り組みの一つです。政府はものづくりの技術振興に向けた施策に関して、「ものづくり白書」を公開しました。環境変化に対応するためには、企業の経営者や組織の能力が重要であり、経営資源の再構成や再結合に必要な能力の強化にデジタル化が有効であると言及しています。また、産業界におけるDX推進は、企業の成長戦略であり、企業でDXが進まない理由として、デジタル技術に関連する知識不足、社内IT部門と他部門との対話不足を挙げています。
参考元:2022年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告) (METI/経済産業省)
製造業におけるDX化の課題


製造DXは、国の後押しがあり進んではいますが、対応すべき課題もいろいろあります。以下に主な2つの課題について解説します。
DX導入のための課題、メリットや導入しないことによるデメリット・リスクなどを徹底解説 – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」
人手不足と製造現場の属人化
日本では、少子高齢化による人口減少が深刻な問題となっています。人口減少により働き手が少なくなることは、マンパワーに依存する製造業界では大きな課題です。加えて、仕事の担当者だけが業務手順を把握するという属人化が顕著なことも製造業ならではの特徴です。ものづくりの水準が高い日本では、以前より現場力が重視されています。しかし、一方で属人化を招いているのも現状です。属人化によって、改善に向けた対応がしづらくなっています。その結果、優秀な人材を獲得できる機会がなく、効率的なものづくりを存続していく体制整備が進まないといえます。
参照元:総務省|平成30年版 情報通信白書|人口減少によって生じる課題
IT投資
最適なIT投資ができないことも課題です。IT投資では、以下の能力を重視した取り組みが行われています。
- オーディナリー・ケイパビリティ:今ある経営資源をより効率的に利用することで利益の最大化を図る能力
- ダイナミック・ケイパビリティ:激しく変化す環境や状況に対応して変革する能力
企業によってIT投資の目的が異なるため、平時の効率性を重視する企業もあれば、不測の事態に対応する柔軟性を重視する企業もあります。国内の企業では、オーディナリー・ケイパビリティを重視している傾向が多いとされています。しかし市場のニーズが変動し不確実性の高い近年は、ダイナミック・ケイパビリティを重視した取り組みが急務といえるでしょう。
参照元:製造業を巡る動向と今後の課題|2020年6月経済産業省製造産業局
データ活用の遅れ
製造業ではDXを支えるデータ活用が遅れています。データの収集と蓄積を進めることはDXに不可欠ですが、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社による令和3年度製造基盤技術実態等調査では生産プロセスによるデータ収集が実施されている企業は6割に満たない程度を推移していると報告しています。製造業ではデータ活用のインフラ作りから始めなければならない状況があります。
参照元:我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査報書|令和4年3月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
資金不足
DXでは資金不足が大きな課題です。製造業では潤沢な利益を得て余裕のある予算を持って事業を進められていることはあまりありません。DX推進には資金がなければならないのは事実で、新しいシステムを導入したり、データを収集するためのセンサーなどの機械も設置したりしなければなりません。本格的なDXをしたいと考えていても資金不足によって始められないのが大きな課題です。
少額の資金で導入しやすいクラウドシステムも増えてきました。しかし、クラウドシステムは継続的にコストがかかるため、中長期的に運用を続けられるかどうかが中小の製造業者では悩みになります。資金繰りに苦労している状況では新たに継続的なコストがかかるシステムの導入を決断するのはリスクが高いでしょう。DXを始めたいと思っても資金が不足しているとなかなか始められないのが実情です。
DX人材の不足
DXを始めるときには自社状況や他社状況を加味して、具体的なプランを立ててDXを推進する必要があります。どのようなDX計画にするかを立案して推進していくDX人材がいなければDXを実現することは困難です。切実な問題として、DX人材が不足していて雇用することが難しい状況があります。DXを推進できるノウハウを持っていて、企業のビジネスに合わせたDXを進められるレベルの人はほとんどいません。
優秀なDX人材を自社で育て上げることも容易ではありません。本格的なDXを今すぐに進めて成功したいと考えても、人材獲得が難しい状況を克服しなければならないのが現状です。導入も運用もしやすくて効果の上がることから順次取り組んでいき、DX人材を獲得できた時点で本格的なDXを計画するのは現代では合理的な考え方でしょう。
製造業におけるDX化を成功させるには?
製造業におけるDX化の成功に向けたポイントを「人材」、「可視化」、「経営単位での実現」の3つ観点からご紹介します。
DX人材の採用
DX化の方針が決定したら、IT技術に精通したスペシャリストを採用する必要があります。DX人材の採用では、データや情報を扱う専門家であると同時に、自社の製造業態にも詳しい人材を採用することが求められます。DX人材がいなければ、DX推進の中核となる人がいないということになるため、DXの推進を進められなくなる可能性も考えられます。予期せぬトラブルが起きた場合に対処が遅れ、さらに大きなトラブルにつながる可能性もあるでしょう。ただし、DX推進に最適な人材に出会えるとは限らないため、社内にいる人材の活用も考慮しながら掛け合わせによる採用を選択肢として念頭に置いておくとよいでしょう。
「見える化」するためのデータ収集
デジタル技術を活用しDXを進めることで、受注からアフターサービスまでのすべての工程に関するデータを収集し、製造現場を「見える化」することができます。その結果、DX推進の課題の一つである「属人化」を解消できるでしょう。また「見える化」の実現により、現場の設備の状況や生産工程などのデータが一元化できるため、問題が起きた場合にも問題点のフィードバック、改善を円滑に行うことが可能です。
製造現場を「見える化」するための手段としては、生産管理システムをはじめ、IoTプラットフォームなどがあります。IoTプラットフォームとは、ネットワークに接続されたIoT機器からデータを収集し、分析や制御などを行うシステム基盤です。
関連リンク:DXツールとは 成功事例や活用状況、導入のメリットや選定時の注意点などを解説
経営単位で取り組む
DX化が進まないケースとして、漠然としたイメージでスタートし、システム部門に丸投げするような例があります。DXを推進していくためには、経営を担う部門が主導していくことが必要です。企業が実現したいことを明確にしたうえで、実現のための具体的な施策をシステムや情報の部門に担当してもらいます。また、製造現場の担当者にもDXのビジョンがきちんと伝わるように、経営部門からDX担当部門、DX担当部門から現場担当者への情報共有を整理しておき、経営単位で取り組みましょう。
製造業におけるDX化の推進プロセス


製造業におけるDX化の進め方は、人材の確保、データ収集、業務効率化、効果検証という流れを意識しましょう。
DX戦略とは?立て方や推進プロセス、成功のポイントもご紹介 – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」
プロセス①人材の確保
DX化の方針を定めたら、DX専門の人材を配置するDX推進部門を設置します。AIなどの技術はだれもが扱えるものではなく、高度な専門知識が求められます。そのため、IT技術に精通したエキスパートを採用しなくてはいけません。しかし、DXに精通した専門家の採用は簡単なことではありません。製造業についてもある程度理解できているDX人材となると、なかなか採用のハードルは高いといえるでしょう。このような人材の確保も製造業DXでは大きな課題となっています。そのため、DX化を進める場合、短期的ではなく、中長期的な計画を立ててから進めていく必要があります。
プロセス②データ収集
人材を確保し、DX推進部門を設置したら、「見える化」するために現場のデータを収集します。現場での作業フローや従業員の数なども整理しておきましょう。さまざまなデータを収集することで、現場が抱える課題の「見える化」が可能になり、現場の課題があぶり出されてきます。その後、有効なソリューションを実施することで、生産効率の良い製造現場に近づけることができるでしょう。またDX化を図るうえでは、製造現場のデータだけでなく、市場のニーズを把握しておくことも必要です。顧客が何を求めているのか、つねに顧客と社会のニーズをつかむことがDX化では重要なポイントとなります。
プロセス③業務効率化
データを収集できたら、業務全体を見直します。効率の良くない部分が見つかったときは改善するために、自動化などの取り組みを実施します。ただし、システムの導入など、大規模に変化させる施策を一気に行うと、現場が混乱し、変化に対応できない可能性があります。DX化に失敗しないためには、最初のうちは、定型業務の自動化など、実践しやすいことから始めて段階的に進めていくことが大切です。まずは、社内でデジタル化していないところを洗い出し、そこから部分的なデジタル化を始めることができるでしょう。DXを本格的に考えるのはその先の段階といえます。
プロセス④効果検証
一つの取り組みを実施したら、実際に効果がみられるか検証していきます。施策に取り組むごとに効果検証を行い、成果を確認できたら次の業務効率化に進むと、スムーズにDX化を推進できるでしょう。また、効果を検証する際に、施策の成否を単に評価するのではなく、達成したいイメージにどのくらい近づけているかも確認することが大切です。
【DX導入事例14選】DX成功事例に見るDX推進のポイントは? – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」
製造業DXの成功事例
製造業DXの成功事例を4つご紹介します。
株式会社リコー
株式会社リコーでは自社のDXを進めつつ、製造業DXの支援サービスも提供しています。リコーの自社での成功事例としてリアルタイムセンサー技術「RICOH EH 環境センサー D201」による品質管理の効率化が挙げられます。
リコーでは複合機などのパーツ生産における温湿度管理においてD201を活用しました。導入前は温湿度計から作業員がデータを集計していて工数がかかっていたのが課題です。月に1~2回のデータ収集だったため、温湿度管理の品質保証にも改善の余地がありました。D201の導入によって自動でリアルタイムの温湿度データの収集が可能になり、作業工数を減らしながら製品品質保証のクオリティを向上させることに成功しています。
参照元:製造業のDX取り組み成功事例をご紹介|RICOH 製造業DX ラボ | リコー
株式会社内田染工場
株式会社内田染工場ではCCM(Computer Color Matching)の導入によって職人芸と言われる染色技術の品質管理を達成しています。内田染工場は顧客重視のテイラーメイドのオーダーへの迅速対応ができることを強みとして顧客からの信頼を得ています。ただ、職人によって染色の際に色味に違いが生まれる場合があったのが課題でした。
CCMシステムの導入によって職人の感性による属人性をなくし、機械によってだ®でも同じ色に染められる仕組みを作り上げました。製品品質を平準化して顧客満足度を向上させるだけでなく、色の検討にかかる作業工程を減らし、業務効率化も同時に実現したDX成功事例です。
参照元:第3節 ものづくり人材に係るデジタル技術の活用の状況
オークマ株式会社
オークマ株式会社では生産システム「IT Plaza」の構築と運用によってDXを達成しました。オークマではNC工作機械の設計・開発・生産・流通を包括的に取り扱うビジネスを展開しています。個別最適の機械開発ができる強みはありましたが、標準化による全体最適を目指し、現場に埋もれている知識を最大限に生かすことが課題になっていました。
IT Plazaの導入によって、概念設計から生産を経て製品を生み出し、顧客からのフィードバックを受ける一連のサイクルを一元的に進められるようになりました。設計・生産プロセスでの知識のデータと、顧客ニーズを統合して分析できる仕組みが整えられ、独自の知識創造を進められるインフラを作り上げるのに成功しています。
参照元:製造業DX取組事例集
沖電気工業株式会社
沖電気工業株式会社では遠隔地にある2つの向上をデジタル技術によって融合させる「バーチャル・ワンファクトリー」を推進しています。沖電気工業では各工場が異なる製品を製造していて、生産・設計・プロセスなどの技術は統合されていませんでした。生産拠点間での部門間融合・生産融合・試作プロセス融合・IT融合の4つを中心にして取り組むことで、個々の工場で育まれてきた強みを融合して成長することが目標でした。
本庄工場と沼津工場での連携では技術交流の活発化によって統一的な技術の確立が進み、外部環境変化への柔軟な対応が可能な協力体制ができました。全体として業務効率が向上したことを受けてコスト削減も同時に実現できたDX成功事例です。
参照元:製造業DX取組事例集
旭化成株式会社
旭化成株式会社は2021年~2023年の3年間連続でDX銘柄に選ばれていて、製造業の中でも先進的な取り組みを続けています。旭化成株式会社ではリサイクル文化をデジタルプラットフォームによって実現することを目指し、カーボンフットプリント(CFP)算定システムの活用をしてカーボンニュートラルを目指して活発なシステム開発を進めています。
旭化成株式会社ではデジタルプラットフォームの活用に特に力を注いでいて新しいビジネス・製品を生み出し続けているのが特徴です。2023年4月にはTIS株式会社との共同開発によって、食品偽造の課題解決になる偽造防止プラットフォーム「Akliteia®」を生み出して活用を開始しています。
参照元:
旭化成、3年連続で「DX銘柄」に選定 | 2023年度 | ニュース | 旭化成株式会社
偽造防止デジタルプラットフォーム「Akliteia®」食品偽装対策への活用を開始 | 2023年度 | ニュース | 旭化成株式会社
山本製作所
山本製作所ではデータの収集・整理と可視化を通してDXを実現しました。各種計測機器やセンサーの設置を通して生産における加工技術の数値的評価を実施したことが特徴で、経営のデジタル化を成功させました。山本製作所ではこの成果を受けてDXセレクション2022でグランプリを受賞しています。
山本製作所ではさらにLAS(Learning Advanced Support)プロジェクトを推進してさらなるDXを目指しています。見える化によるDXを成功させたことを受けて、「ものづくり力」の維持向上のためにAIによるデータ活用も取り入れて、機械加工最適化支援サービスという新しいビジネスを生み出して競争力を手に入れています。
参照元:DXセレクション2022 「グランプリ」受賞 | 株式会社山本金属製作所
バイホロン株式会社
バイホロン株式会社は富山県に拠点を持つ健康食品のOEMメーカーです。バイホロン株式会社ではSDGsの取り組みの一環としてペーパーレス化を推進し、基幹システムの全面的なシステム化による生産管理と工程管理の徹底をするDXに成功しています。
バイホロン株式会社では受託製造をするため、顧客ニーズに合わせた生産を進めることが重要な課題です。HTシステムや作業実績記録システムなどが存在していたため、既存システムを含めて一元管理できる基幹システムを構築したのが特徴です。結果として、品質情報管理や在庫管理、生産計画などをすべて紐づけて業務効率を向上させることに成功しました。実績データを蓄積してシステムのさらなる改善にも取り組んでいます。
参照元:【バイホロン株式会社様】健康食品OEM受託製造業としてシステム基盤(基幹システム)整備の為にJIPROSを活用[導入事例] – 製造業向け生産管理システムJIPROS
関連リンク:業界別のDX事例15選 DXが各業界にもたらす影響や変化とは
製造業におけるDX化は「SMS」から始めよう
SMSの活用はDX化の第一歩といえます。例えば、製造業におけるSMSの活用事例としては、シーズンになるとメーカーにエアコン修理の問い合わせが殺到し、対応しきれないという課題がありました。しかし、シーズンが始まる前にSMSを使って試運転を呼びかけたり、SMSで取付けや修理の訪問日をリマインドしたりすることで、解決できました。またメールやDMで販売促進をしたものの、読んでもらえず効果を実感できないといった課題も到達率の高いSMS配信が役に立ちました。
法人向けSMS送信サービスなら「KDDI Message Cast」
KDDI Message Castは、SMSで確実性の高いメッセージを送れるサービスです。二段階認証、重要なお知らせ、料金督促などの通知・連絡手段として多くの企業にご利用いただいています。導入実績は、地方自治体、病院、不動産管理会社、クレジットカード会社など、さまざまな業界にわたります。国内3キャリアと直接接続のため、配信品質と到達率の高さで伝えたいメッセージを確実に届けることが可能です。また、24時間365日の監視運用サポート体制を確立しており、故障発生時には迅速に対応します。SMS送信サービスなら、ぜひKDDI Message Castをご検討ください。
まとめ
IT技術の発展により、製造業で人が行ってきた業務の大半を機械が担えるようになりました。IT化により、工程を一元管理し、生産性と安全性を高め、かつコストを抑えながらDX化を目指すことが肝心です。DX化は、実現したいイメージを明確にしたら、まず必要なIT人材を確保します。そしてデータの収集や分析を行い、市場のニーズも把握しながら進めていきます。DX施策の全てを一気に実現するにはコストと時間がかなりかかってしまうため、まずは取り組みやすい内容から始めましょう。
その他のDX関連
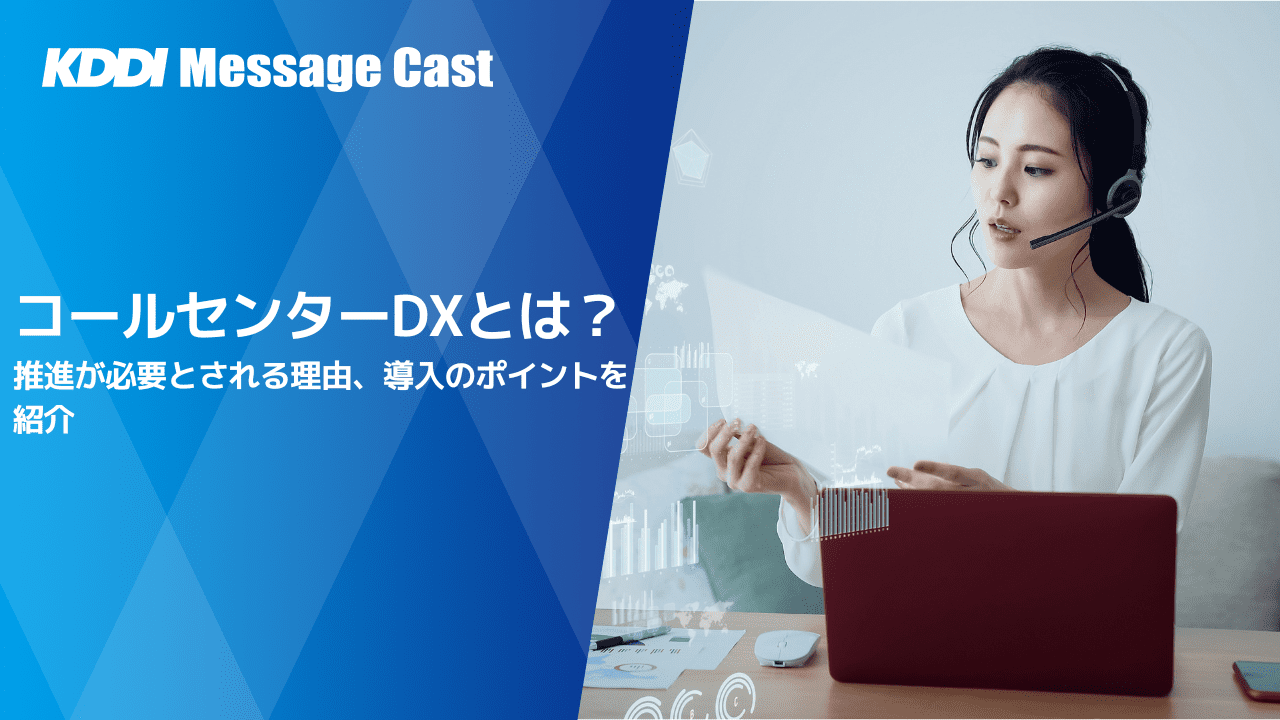
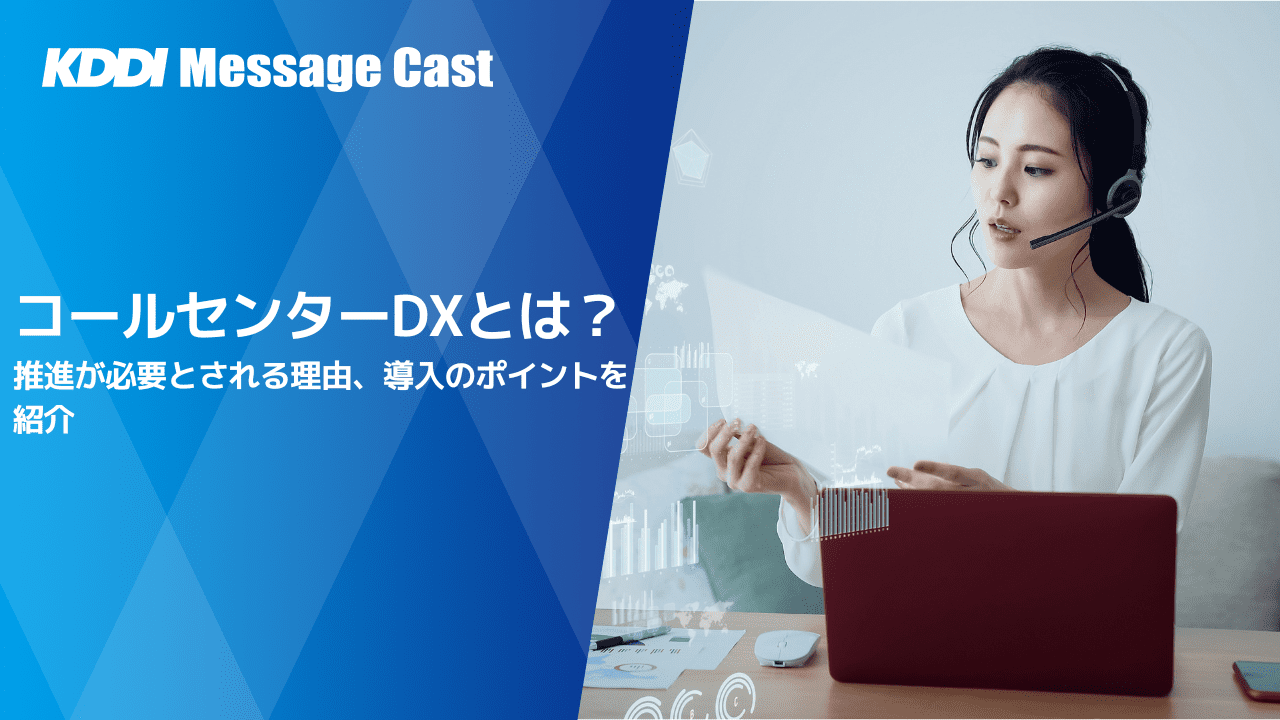
コールセンターDXとは?推進が必要とされる理由、導入のポイントを紹介


人材業界におけるIT化・DX促進とは?活用例も解説
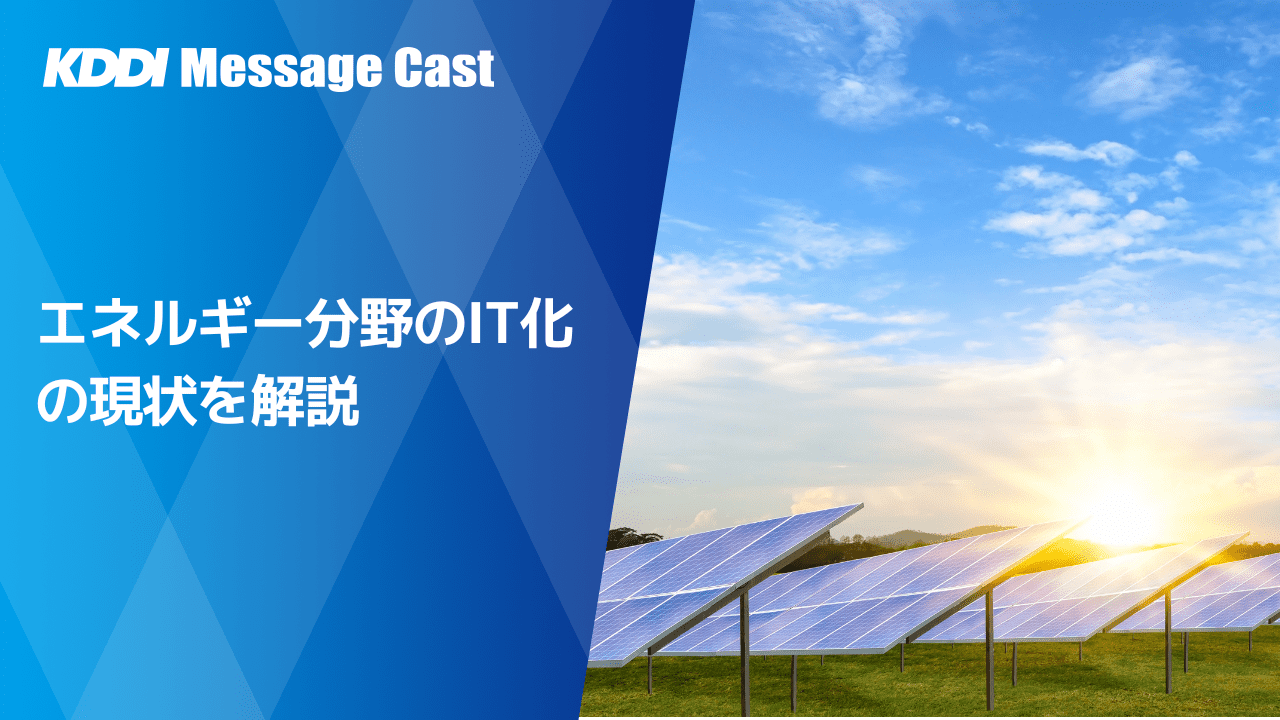
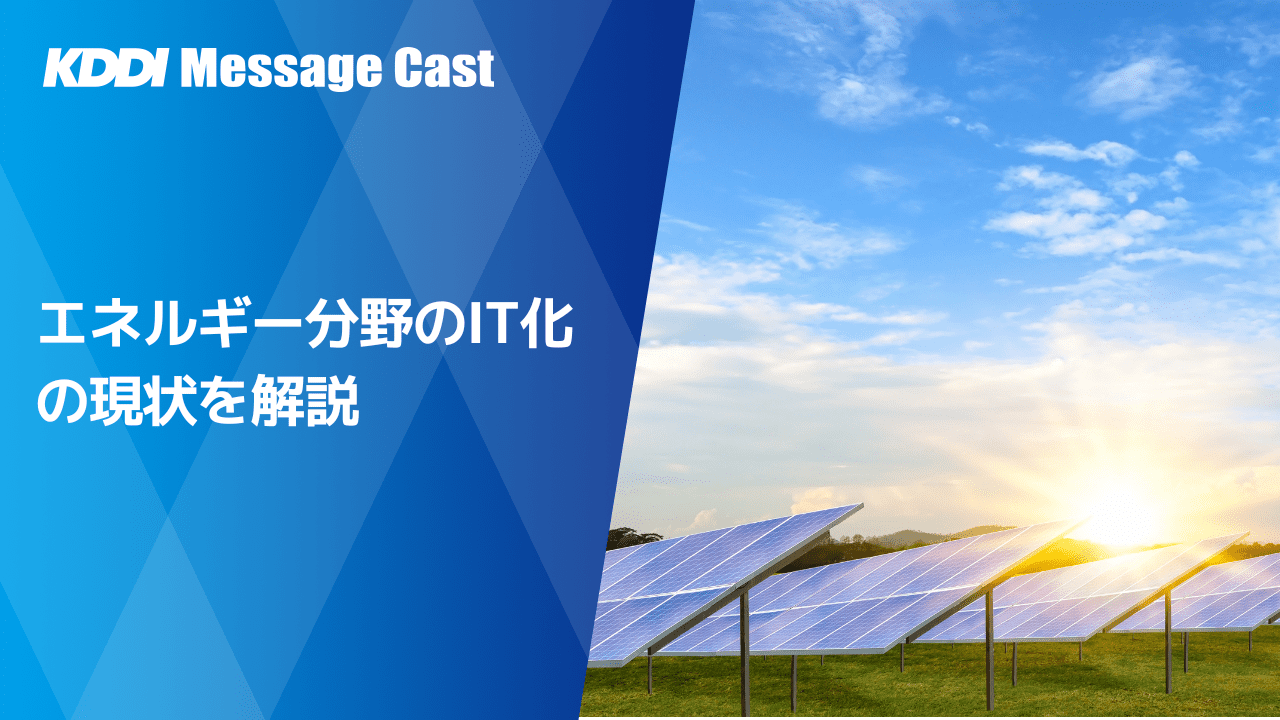
エネルギー分野のIT化の現状を解説


人材業界の業務を効率化して情報共有における課題を解決しよう


人材業界でペーパーレス化を進めるメリットやデメリットは?方法や成功事例を紹介